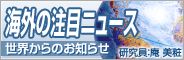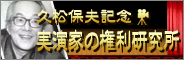第一章―アジアの音楽史「江戸歌舞伎はチンギスハーンがいなかったら誕生しなかった!?という物語」
大野遼のアジアの眼
NPOユーラシアンクラブ 会長 大野 遼
【プロローグ 現代史の中の二人の日本人】
―帝国主義的謀略の時代に「アジアの眼」を獲得した江上波夫と木村肥佐生― 私は、「アジアの時代」が、国家・民族・宗教を超える方向で進行している、と考えて活動している。 血眼になって、小さな島の領有権を問題にする意識は、人類が「国家」というものの原型を作ったアケメネス朝ペルシャの時代に遡るが、そろそろその終焉に近づいていると信じている。しかし日本という国は、第四の植民地帝国という現代史を背負って、アジアの趨勢に対応できていないように見える。アジアと正面から向き合う日本人が増えないと、日本もアジアの未来も少し心配だと通信社の記者を早期退社して、砂漠に水を撒いたり、太平洋を泳いだりしているような活動を続けてきた。国家・民族・宗教を超えて「民族の共生」「自然との共生」を模索する。特に少数民族、先住民族にウェートを置いてというのが私のお題目である。この文章で紹介しようとしているのは、正面から向き合う「アジア」とその理解、「日本とアジア」という時の日本人の理解の不思議、「日本と日本人の中のアジア」、「アジアから見える日本」などについて、ここ15年ほど特に重視して取り組んできた「音楽」をキーワードにしながら、その殆ど知られていない話題や視点を提供しようと思います。 とはいえ、その前に、「アジアの眼」や「アジアの目線」を考える時に、まず最近の私の行動に即して、二人の日本人を紹介することは有益だと考えたので紹介する。 先日(8月3日〜8日)、中華人民共和国内モンゴル自治区東スニット旗を訪ねた。現地地方政府や議会関係者等が昨年、神奈川県愛川町のあいかわ公園で開催した「中津川モンゴルフェスティバル」に代表団を送り、モンゴル相撲(ブフ)トーナメントに参加し、町内の食肉企業や小学校を視察した後、愛川町に対して友好町(旗;内モンゴルの町に相当)を提唱して帰国したのに対する、民間レベルの視察団(10人)の一員として参加したものである。町レベルの国際交流の促進は私の意図することに適うため訪問したが、この際に標題の二人の日本人が、このモンゴル最大の草原の一つタムチ草原からゴビ砂漠にかけた関東平野の二倍に相当する行政区を占める東スニット旗に足跡を記していることに思いをいたし、「アジアの眼」と題するこの一文のプロローグにふさわしいと考えて記録しておくことにしました。

江上は、戦後「騎馬民族征服王朝説」などで、日本の考古学界、東洋史学界、民間の古代史ファンの間で話題になった人であるが、私が、通信社在職中から設立、事務局長として運営にかかわった北方ユーラシア学会の会長であり、座談会等にご一緒させていただいたこともあり、今回の視察で、江上も訪ねたというエンゲルゴル、オボを訪ねながら奇縁に感じられた。江上は、前年北京大学留学生の時に3度の内モンゴル旅行を行っており、昭和6年(1931年)、東亜考古学会の調査団4人の中心的なメンバーとして、中国における遊牧民族と漢民族の境界都市である張家口から「単なる遊歴のように偽装して」内モンゴルの東半部1,150キロを二頭引きの荷馬車を主な乗り物として6月28日から8月27日まで踏査していた。江上は当時まだ20代だった。この時の経験が江上の騎馬民族説の背景となり、そのルートに、私たちが訪れた東スニットも含まれていた。江上は、驚くべきことに、「その(調査の)間我々は完全に世間から隔絶し・・・中村大尉事件(6月27日)も万宝山事件(7月2日)も知らず・・・そして北平に帰った翌日であった。あの満州事変勃発(柳条湖事件)の号外を手にしたのは!・・・」(江上波夫の蒙古高原横断記/池内紀編・解説)と記している。現実離れした学者の真骨頂とでも言うしかない。東スニット旗に足跡を残した学者には梅棹忠夫(のちの国立民族学博物館長)もいた。1944年、善隣協会・西北研究所の嘱託研究員として民俗資料の図録を残し、モンゴル人研究者の間で喜ばれている。陸軍、そして海軍による謀略的事件につながる、不穏な時代への転換期に、関東軍や満州鉄道の援助を受けての調査であった。戦後の史学界、文化人類学界の錚々たるメンバーが、陸軍の謀略的行動と表裏の関係で現地調査していた時代であった。江上は、2002年、多くの研究者に惜しまれて亡くなった。


東スニット旗にゆかりのあるもう一人の日本人は木村肥佐生。江上が調査した年に発生した柳条湖事件を発端として昭和7年、満州国の建国が宣言され、9年に、溥儀が満州国皇帝になる間、実は並行して、内蒙古対策も行われていた。チベット仏教学の多田等観は関東軍に、自治運動の起こる内蒙古について「内蒙古には当分の間政治工作・軍事工作は行わず、経済工作」を行うよう提案し、内蒙古善隣協会は獣医の派遣等を行っていたが、この内蒙古対策は満州国建設の裏工作を指示していた元関東軍参謀総長小磯国昭の意向に沿っていた。この善隣協会は「(日本が)西北へ出て行く謀略機関」(藤枝晃)でこの下に中学卒業した若者を諜報員にしたてる機関が興亜義塾。木村肥佐生は、1939年、17歳の時応募し、1940年二期生となり、外モンゴル(北モンゴル、現モンゴル国)と接する東スニットの地で、モンゴル方言を吸収しモンゴル人になりきり、1943(昭和18)年10月。21歳の木村肥佐生はモンゴル人巡礼ダワ・サンボとして、モンゴル人夫妻ダンザンハイロブ、ツェレンツォーとともに、内蒙古東スニット旗のザリン廟からラクダにまたがって巡礼の旅に出発した。「新疆ウイグルに着いたなら隠れスパイとして現地に潜み、情報を収集して日本軍の到着を待つ」のが任務であった。私は今回の東スニット視察で副議長にお願いし、わざわざこのザリン廟に連れて行ってもらったが、荒れ果てた村の一角の廟は家畜小屋と化し、歴史の狭間の日本人の運命は全く過去のものとなっていた。木村は、45年5月、新疆ウィグル自治区から転身し9月、チベット・ラサに向かい、日本の敗戦を知る。インドのカリンポンで「国家に足をおいた生き方というものは、浅い生き方ではないのか」ととりあえずモンゴル人のまま生きていくことにした木村は、英国情報部に関係もあるタルチン・バブーというチベット語新聞を発行している人物と出会い働くようになった。そして11月、興亜義塾3期生の西川と再会する。西川は内モンゴルからずっと徒歩で、ヒマラヤを超えカリンポンまで、チベット仏教の僧として旅をした。西川はチベットとインドの密貿易、木村は新聞社の下働きの傍ら、チベット語とドクター・グラハムズ・ホームというアングロ・インディアン(イギリス人の父、インド人の母の間に生まれたユーラシアン)と呼ばれる混血児を対象とした学校で英語を学ぶ。1947年には、英国情報部の依頼で、中国がチベットを侵略する可能性を探る探査行に西村とともに出掛けた。カリンポンは英国、ロシア、中国、チベット人のスパイが交錯する情報都市で、木村は一時チベットの反体制派と一緒に活動した。木村と西川は1950年帰国し、木村はGHQで、西川は郷里に帰りそれぞれ別の人生を歩んだ。木村はダワ・サンボとして亡くなったという。 江上波夫と木村肥佐生は、いずれも日本の国策の狭間で大陸に視野を開いた人であった。二人とも、国家という存在を客観的に見るようになったという点で共通している。江上は、「騎馬民族」の強力な支配を日本の基層文化に見ようとした点で、木村は、謀略の対象とされたモンゴル人やチベット人の目線で日本を見ようとした点で、国家の時代にほんろうされた一般の日本人とは違う目で日本という国家に向き合った。二人の目線の共通性は「アジア」から見る日本という点に収斂されると考えられ、「アジアの眼」を持った人であった。
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。