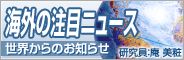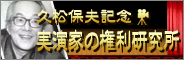第二章―アジア源流「〝幻の河オクサスから世界は始まった〟という物語」 その10
大野遼のアジアの眼
NPOユーラシアンクラブ 会長 大野 遼
【ゼラフシャン川流域に南下したアンドロノヴォ・ペトロフカ文化のインド・アーリア人】
―青銅器の原材料採鉱を求め、後にソーマを痛飲暴徒化し、BMAC、インダス文明を侵略!?―
神「銅器時代」(金石併用時代)とともに形成された農耕都市文明の鉱石需要に応える交易ネットワークの中で1.絵文字(古拙文字)から楔形文字が誕生し、歴史時代を刻むようになり、2.ヒ素から錫を使用する青銅器の製造が始まり(紀元前2800年頃)ヒンズークシュ西方が重要な錫山地として役割を増し、3.アジアの流動性が高まり、2004年、エラム人の侵入で第三シュメール王朝が亡び、アジアの東西交易ネットワークの要としてBMACが、古アッシリアを視野に「錫の道」のセンターとして機能した可能性について触れた。そしてそのBMACの北側には、カザフスタンからウラル山脈にかけた地域を中心として活発な活動を展開していた、チャリオット(二輪馬車)を特色の一つとする青銅器時代の牧民文化、アンドロノヴォ文化がやって来ていた。
● 紀元前1800年頃突然消失したBMACとインダス文明
BMACは、インダス文明より300年ほど遅い紀元前2300年前から紀元前1800年に形成され、紀元前2000年前後に、アムダリア川上流のラピスラズリ、アフガニスタンでの「錫」、ゼラフシャン川上流の銅や金の入手、加工、交易で独占的地位を得て、最後は「突然の出来事」で放棄されている。つまり「BMACは、後に知られるインド・イラン的世界(ソーマ/ハオマを利用し、拝火儀礼を伴う)に影響を与えたもしくは関わりのある文化を内包している」とは認められるものの、BMACは突然消失し、後にアヴェスタやリグヴェーダに記される馬車によって象徴される遊牧民の世界につながる「継承性」の証拠は認められないのが現状である。しかも無文字文化(未解明の絵文字)の歴史の議論では、考古学者によるBMACの年代比定(紀元前2300年から1800年)とリグヴェーダやゾロアスターが語られた時代についての言語学者の比定(紀元前1500年に北インドパンジャブ地方に進出し武力で先住民を制圧し、紀元前1000年頃ガンジス川中流域に移動した時代に残されたのがリグヴェーダ、紀元前1000年頃に語られたのがアヴェスタのガーサー)との間には、300年から800年の時代の溝がある。放射性炭素年代測定等でこの溝は狭まったようであるが、「継承性」の証拠と合わせ、BMACとリグヴェーダ、アヴェスタとの年代ギャップは、BMACをどう理解するかという課題を残している。 BMACの遺跡群には、二重三重の外壁に囲まれた円形、方形の大建築物が特徴の一つであるが、この理解の仕方については、サリアニディ氏が「北部メソポタミア」を原郷とすると考えているのに対して、中央アジア考古学に通暁したV.M.マッソン氏はインダス文明のハラッパ―の影響を考えている。 BMACもハラッパ―も1800年頃に突如歴史が途絶し、BMACには、拝火祭祀やソーマ・ハオマ製造などリグヴェーダ・アヴェスタに残された文化表象はあるものの、馬や二輪の戦車を表象とするミスラ(ミフラ)やミトラに代表される遊牧畜的特色を欠いている。
● ソーマを痛飲し戦闘に赴くインドラは先住民の殺戮者、鉱石ネットワークを破壊

リグヴェーダやアヴェスタにおいては、馬に牽引された「戦車」を象徴する世界は共通しているが、リグヴェーダでは特に、ソーマを痛飲し陶酔して戦闘に赴くインドラの姿が際立っている。インドラの記述(「リグヴェーダ讃歌」辻直四郎訳、岩波文庫)の「インドラの歌」の冒頭で、インドラは、水のシンボル「アヒ」(蛇=ヴリトラ)を殺して、「ダーサ」(先住民=悪魔)の妻であり、「アヒ」に監視されていた水を穿ち出し、山々の脾腹を切り裂いて出口をつくり、七河を流出させたと表現され、「ヴァラ」(悪魔)の囲みを開いて牝牛を駆り出し、二個の石の間に火を生み・・・「ダーサの色」(黒色の原住民)を屈服せしめ、消滅せしめた後、勝ち誇る賭博者のごとく、勝利を博して、賭物たる部外者の豊かなる財産を収得した―と、「先住民の掠奪者」の表象のように描かれている。「リグヴェーダ」に記されるインドラのキャッチコピーは、「馬も、牛も、村人(軍隊)も、全ての戦車も服従する、太陽を、暁紅(朝焼け)を生む、水の指導者」「大いなる罪を犯すあまたの者どもを、彼らの気づかざるあいだに、矢もて殺したる」「倨傲(驕り高ぶる)なるものに、倨傲を許さざる」「ダスユ(原住民)の殺戮者」など、太陽を表象とし、戦車を操る戦闘神、先住民の侵略者であることが明示されている。戦士あるいは戦士を鼓舞する神の色合いが濃いインドラには誕生の物語があり、「インドラは母の脇腹から誕生」し、「母から捨てられ」、「父を殺し」、「(インドラの)母は、水牛(インドラ)のあとを見送れり」と記され、“遺棄された若者が、困窮しながら自立する過程でソーマと出会う”といった風情がインドラには漂っている。ソーマを痛飲し陶酔して意気上がる(悪事を働く)若者であれば、現代にも通じることである。そしてこの“遺棄された若者”が、古代遊牧社会にあったとされる傭兵の祖でもあった。 この馬車が牽引する戦車の発明者が、インド・イラン系アーリア人の祖と考えられるアンドロノヴォ文化を形成した人であった。今のところ最古の二輪戦車はウラル山脈南東に位置するシンタシュタ遺跡(紀元前2000〜1800年)の竪穴式埋葬施設で発見されたのが最初である。この戦車が戦闘にどれほど活躍できたのかは議論のあるところのようであるが、その「用途」については、学者たちが考えるのと私が理解するのとでは少し違う。後続のペトロフカ文化の人々は、中央アジアサマルカンド付近に移動した。そこはバクトリア―マルギアナ複合に特徴的な金属製品が出土していると指摘されているゼラフシャン川流域であった。

アンドロノヴォ文化と、「北メソポタミア」あるいは「ハラッパ―」系の中央アジア先住民であるBMACとの同化、融合が始まったと受け止められる現象の一端とみる。アンドロノヴォやペトロフカといった遊牧系集団の文化は中後期青銅器文化に属し、その文化形成の基礎には「銅」「錫」を入手しなくてはならないという「青銅器冶金文化」のニーズがあった。もちろんBMACも「銅」「錫」を入手する格好のポジションに形成されていたのだが、アンドロノヴォ・ペトロフカ遊牧民にとっても、「原産地」は欠かせない場所であり、そこにBMACという魅力的な鉱石ネットワークの要に位置して繁栄する都市文化が広がっていたのである。 BMACが、遊牧民文化であるかどうか、といえば、オクサスとゼラフシャンの水系、デルタを利用した「鉱石ネットワーク」の要に位置した都市文化であると言うべきだと思う。農耕や少しばかりの牧畜はあっても、採鉱と冶金、商業ネットワークが都市文化の原点であったと思われる。そこに新たに、牧畜を主軸としながら、青銅器文化の原点である「銅」「錫」を求めて南下し、ゼラフシャンとオクサス流域に流れてきたのがアンドロノヴォ文化の人々(シンタシュタ・ペトロフカ文化の人々)であった。彼らの目に見えたBMACは「銅」と「錫」で栄えた交易のセンターであって、ペトロフカ文化の人々もBMACの周辺で採鉱し、繁栄するBMACの文化に触れ、さらにバクトリアの南に拡がる「錫」産地にも足を延ばし、「北メソポタミア」につながるアナウ系農耕文化やヒンズークシュを超えたインダス川の上流地域の都市文化も目にしていただろう。

実は、地球の歴史では地球規模の気候変動は何度も起きており、最近の大きな気候変動では今から6000(紀元前4000)年前に最も温暖になった(現在より2-4°高い、ヒプシサーマル期)が、この時期、日本では縄文海進が起き、サハラ砂漠は緑で覆われていたとされ、北インドからカスピ海東部に至る「ユーラシア雑穀センター」(阪本寧男元京大教授)でのアワ、キビ等の雑穀農耕が中央アジア経由北アジアに拡散された。この頃銅が使用され始め、雑穀農耕が始まった形だ。シュメール文化(紀元前2800年頃)で始まったヒ素から錫を使用した青銅器製作が、採鉱製錬、冶金の鉱石ネットワークを活性化し、アフガニスタンからアムダリア流域の重要性が高まったことは前稿で紹介した。この金属精錬時代に突入したことで人類は地球上の森林を大量に伐採する自然破壊の歴史を刻むことになるのだが、上記雑穀農耕と「錫」冶金青銅器が北方に伝わり形成されたのがアンドロノヴォ文化である。つまりアンドロノヴォ文化(シンタシュタ、ペトロフカ遺跡等)は、馬が引く二輪「戦車」によって機動性が高まった遊牧畜と雑穀農耕に従事する人々によって形成されたのであるが、元々カスピ海東方から北インドにかけて存在した雑穀センターの農耕と金属精錬の技術を持った人々の北進や影響の下で成立したことから南方の繁栄する鉱石ネットワークや農耕を基盤とする都市文化は常に視野にあったと想像される。アンドロノヴォ文化の人々は、発明した馬が引く二輪「戦車」によって機動性を高め、鉱石(銅、錫)を求めて南下したのである。またヒプシサーマルの最盛期の後、紀元前2000年頃から急激に気温が低下し、乾燥化したことも、農耕や牧畜環境が変動し、移動の原因となったと考えられる。少なくともアンドロノヴォ文化の初期(ペトロフカ文化)の「戦車」は、錫・銅鉱石を入手・採鉱し、運ぶために使用されたのであって、アンドロノヴォ文化が中央アジアを中心として東西南北に広範に拡大されることにつながった。牧畜民が発明した馬が牽く二輪「戦車」は、当初採鉱運搬に便利な、現代で言えば農業用軽トラックの機能を持ったと考えられる。
● BMACの住民は、インダス文明・ハラッパー出身
今のところ、考古学者がBMACとインド・イラン系を結びつけるのに対して、文化の継承性から疑問を提示し、反対しているのが言語学者である。2人の意見を紹介する。A.ルボツキーは、BMAC発掘責任者であるサリアニディ氏の生誕80歳記念論集「文明発見記念論集」に論文を発表し、「(BMACを)創始した人びとについて、しばしばインド・イラン人又はアーリア人が議論の俎上にのぼっている。例えばサリアニディは、かれらこそがゴヌル(BMACの宮殿)の創始者であると確信している。アーリア人は何者で、彼らはこの文明の創始者だろうか」と問いを発し、「アーリア人がゴヌルの創建とは無関係」と結論付け、リグヴェーダやアヴェスタの語彙ファンドに基づいて、「アーリア人は遊牧民であったとの議論の余地のない結論に達する。彼らには、馬、馬装具、馬車、さらにはさまざまな家畜名に関する数十の単語があったが、農耕に関する用語はごく限られている。そのほか、彼らの言語には建築関係は事実上なく、宮殿や神殿などの語は全く見られない。このことから得られる結論は、アーリア人はゴヌルのような都市を創る状態にはなかったということである。さらに、彼ら遊牧民にとって、そのような都市は不必要であった」と指摘した。そして「アンドロノヴォ人がバクトリアとマルギアナの農耕民と密接な関係を保っていた」「もしアンドロノヴォ人が実際にアーリア人であったなら、この接触は原インドイラン人の言語の中に借用語として残っているはず」として、「牧畜民であるアーリア人が、彼らの品物を売るために都市を訪れ、たいへん驚いた」結果として、借用語として、建築関係の語彙、排水溝など給水に関連する語、ソーマ/ハオマも「アーリア人がバクトリアとマルギアナの住民から借用した」、ラクダやロバも「アーリア人は北方から中央アジアに来たので知らなかった」借用語だと紹介している。結論として、「この言語は、これまで知られているどんな言語にも似ていない。ただし、音韻的、文法的にそれを現存の言語と比較してみることはできる。・・未来のインド人(インド・アーリア人)がヒンドゥクシュ山脈を越えて南下した後のサンスクリット語の特徴にたいへん近い」「つまりパキスタンの原住民の言語とバクトリア―マルギアナの言語が近いこと、ゴヌルの住民はパキスタン出身であった可能性がある」と考えを述べ、ロシアの人類学者ババコフらがゴヌルの墓地で発掘された頭骨を研究した結果、「ゴヌルの頭骨はアルカイックな形態とヴェーダ的住民に近いことから、ウズベキスタン南部と北部パキスタンおよび北部インドの住民に最も近い」と結論を出したことと一致すると結んでいる。つまり、BMACはインダス文明のハラッパ−の影響を考える考古学者V.M.マッソン氏の説を補強する。
● BMAC消滅の後、カスピ海南西でミタンニ王国が誕生、インド・アーリア系が支配層
もう一人の言語学者が後藤敏文・東北大学大学院教授。後藤氏は、「(BMACの発掘者であるサリアディニ氏はBMACの)城塞都市そのものをインド・イラン系の人のものとするそうであるが、『リグヴェーダ』で『城塞』と紹介されることのあるpur-は木の杭などで作った仮設の柵であり、アーリヤ人が立派に石を積んだ城塞を造りえたとは到底思えない。むしろ、インド・イランの人々の来襲から自らを守らなければならなかった『平和で』豊かな人々が築いたものであろう」(「インド・ヨーロッパ語族−外観と人類史理解に向けての課題点検−」)、「サリアディニ自身の見解は無理だと思います。つまり、インド・ヨーロッパ語族のインドイラン語派の人たちの居城だというのです。そんなことは考えられません。移動する遊牧略奪民族であり、物質文化を軽蔑していた人々に、あんな頑強な都市があったら厄介で生活できないでしょう。彼らはむしろ平原を閉ざす、土地を囲い込む人々を敵視しています」(「一神教と多神教:インドの《一神教》理解について)と指摘、クルガン文化の発掘者として知られるマリヤ・ギンブタスの指摘する、紀元前5000年〜紀元前3000年の間に、インド・ヨーロッパ祖語を話す攻撃的な人々が、女性中心の村落社会を侵略したという、西方ヨーロッパで起きた現象に対し、アジアにおける現象がインド・アーリアとBMAC,インダス文明との遭遇であったと語る。 私は既に触れたように、BMACは、銅と錫の採鉱と流通のネットワークのセンターとして形成され、それがカスピ海を超え、北メソポタミアで誕生した古アッシリアとヒッタイトの「錫の道」とつながっていた可能性について指摘した。このBMACが「突然」姿を消し、BMACの東ではインド・アーリアがヒンズークシュ山脈を越えているが、BMACの西では、古アッシリアとヒッタイトの間の「錫の道」が終了(BC1750年頃)している(「古アッシリア時代の錫交易と土器の分布」小口裕通)。この古アッシリアを属国にしたのがミタンニ王国であった。ミタンニ王国の中心は、カスピ海と黒海の間、コーカサス地方の北から南下したあるいはカスピ海の東方ホレズムからやってきたと議論されるフルリ人であるが、支配層を形成した王族・貴族は、インドに進出したインド・アーリア系戦士層であった。ヒッタイトの首都ハットゥシャとされるボガスキョイ遺跡で発見された楔形文字で残された契約・条約文書では「ミトラ、ヴァルナ、インドラ、二柱のナーサティヤに誓う」としてリグヴェーダに登場するインド・アーリア人の神々を挙げて、ミタンニ王がヒッタイトの王女を迎え、ヒッタイトの王に王冠を贈る契約を含み、戦車で使う馬の調教師のキックリの文書には、aika(サンスクリットのeka、1を意味する)、tera(tri、 3)、panza(pancha、5)、satta(sapta、7)、na(nava、9)、vartana(vartana、丸い)といった単語が使われ、ほかの文書にはbabru(babhru、茶色い)、parita(palita、灰色の)、pinkara(pingala、赤い)といった単語が含まれているという。BMACを破壊し、パキスタンやインドの北部でインダス文明を形成した人びとを殺戮したインド・アーリア人が、西は北メソポタミアに移動し、「錫の道」を崩壊させ、古アッシリアを滅ぼし、ミタンニ王国を形成した形である。アンドロノヴォ文化の遊牧民が、気候変動(寒冷化、乾燥化)による牧畜環境の変化および青銅器の原材料である銅や錫を求めて、馬が牽く二輪の「戦車」を駆ってゼラフシャン川一帯(サマルカンド付近)へ進出、採鉱搬送の運搬車両として活用したり、BMACと交易や運搬に従事する中で、「倨傲(驕り高ぶる)なるものに、倨傲を許さざる」というインドラの”身勝手な理屈”で、繁栄する南方のBMAC社会や「錫の道」を破壊するに至ったと想像する。
● アンドロノヴォ系遊牧民で形成された棄民的若者が共有した男性結社、選民意識で侵略
この過程で形成されたのが「インドラ」「ミトラ/ミスラ」に代表される宗教的若者戦士集団(男性結社)「マイリヤ」「二本足の動物の群れ」であった(「アーリヤの男性結社」スティル・ヴィカンデル論文集、前田耕作編、「ゾロアスター教論考」ゲラルド・ニョリ、前田耕作編)。BMAC社会との接触で知った、ソーマで酩酊した若いマイリヤのメンバーが、血塗られた棍棒で人や牛を虐殺し、女性と乱痴気騒ぎを起し、当初は採鉱運搬の「戦車」であったチャリオットを文字通り戦車として使うことも行われるようになった。それがBMACやインダス文明が「突然」姿を消した原因であったと想像する。上記ヒッタイトの首都ハットゥシャで発見されたボガスキョイ文書の中にも「マリアンニ」という支配的戦士層を表わす言葉が知られるという。アンドロノヴォ文化だけでなく、銅器、青銅器時代に入った牧畜民は遊牧民化してくるが、特有の男系社会を維持する為に「口減らし」的な移民と「銅」や「錫」を採鉱したり、南方の鉱石ネットワークの要衝に形成された都市建造物の周囲で、鉱石の運搬や交易に従事する者もあったと想像され、こうした棄民的若者の間で共有されたのが男性結社と考えられる。インドラに見られる「棄民」的表象は、こうした南下した牧民の若者の社会現象を示しているのではないか。その社会現象の中には、後にエジプトやギリシャ、ローマ等で傭兵として活躍するサカの遊牧民も含まれる。そして男性結社の中から生まれた人狼伝説が、アヴェスタのホーム・ヤシュトで非難される「両足のmairyo」「四本足の狼」、ウ・ディーウ・ダート(「悪魔(ダエーワ)に対抗する法」の意)で「両足の狼」「両足のmairyo」と関わる(上記「アーリヤの男性結社」)との指摘も、その社会現象の一部を示している。アンドロノヴォ系ペトロフカ文化の形成地はインドア・アーリアの故地でもあるかもしれない。そこはサマルカンドを中心としたゼラフシャン川沿いであり、のちにユーラシアの商人として知られるソグド人揺籃の地であった。かれらは北方においては、蜂蜜で作った蜜酒を飲んでいたが、BMACと接触することでソーマを知り、若者たちの間でソーマを痛飲し酩酊することで意気上がる者も現われ、「倨傲(驕り高ぶる)を許さず」といった理由で侵略を開始したのがインド・アーリア系という「先発アーリア人」誕生の一端を示していると考える。ドイツやアメリカで誕生し、今でも根強く活動する人種差別的組織形成の根は深く、今も続くローマ帝国の東西の子孫たちが始めた植民地時代の国家を形成する優勢な勢力が有する「選民思想」は、銅器、青銅器の普及と共に形成された北方型牧民社会が促した「口減らし」的若者による戦士団が、銅器、青銅器文化の中で形成された農耕都市文化の領域に進出し、接触融合し、侵略し植民地を形成する歴史の中から生まれ、戦士団の中核となった若者の高揚した気分の中に淵源があり、ヨーロッパの諸民族の歴史を刻み、春秋戦国時代の中国や北方アジアの牧民史の形成の刺激となっていく。リグヴェーダを生んだ北西インドのバラモン教(後のヒンズー教)によるアーリア人の優勢支配の構図(カースト制度)もこうして形成された。 ギンプタスは、「クルガン文化」について、暴力的な男系集団が、ヨーロッパのそれまでの女系農耕社会を侵略した表象として提言しているが、インドにおいてもインドラが「ヴリトラ(蛇)」を殺し、七河を解放した、というのが、インダス文明の農耕都市文明の周辺にいた男系集団が女系社会を襲い、殺戮、滅ぼしたことを記していると受け止められる。
● 飲み過ぎへの戒めや痛飲しての非道(悪)との戦いから誕生したゾロアスター教
ゾロアスターが草創したアヴェスタのガーサーは、こうした目を覆う「インドラの非道」(悪)への批判と戦いとして現われたと考えられる。アヴェスタのホーム・ヤシュト第十章(「原典訳アヴェスター」伊藤義教訳)には「(ハオマを)飲んでも、牛や幡のように、わたしが勝手に、蹣跚(酔ってふらふら)することのないように、・・・強力な霊見を欠くマルヤ(酩酊した戦士団)・・・女(戦士団に伴う娼婦)の無用さを追放します」とハオマの効用は認めながら、飲み過ぎへの戒めや痛飲して非道を行う「悪」との戦い「善思善語善行」が打ち出されているのがゾロアスターによる宗教革命の方向であった。こうしてインド・アーリア人がヒンズークシュ西方の東イラン(現アフガニスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン)からインド北西部、パキスタン北部へ移動し(あるいは追われ)た後に形成されたのが善の創造主アフラマズダが創った「一六国」であり、その中央を流れる川こそオクサス河(旧アムダリア河)であった。次の稿では、オクサスの地下水脈の謎を紹介する。
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。