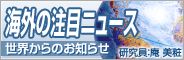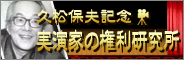第二章―アジア源流「〝幻の河オクサスから世界は始まった〟という物語」 その12
大野遼のアジアの眼
NPOユーラシアンクラブ 会長 大野 遼
【金星となったアナーヒターは人類の未来への警鐘】
父権的好戦的遊牧民が「古ヨーロッパ」と「アジア」の女系農耕社会を征服 「地下水脈」(アナーヒター)が人類史最初の最大の帝国誕生の基盤
―ゾロアスター教が世界宗教形成に影響を与える―
オクサス(プラアムダリア)は、北方遊牧(後の騎馬)民族と南方農耕都市文明との出会いの場所であり、契機は、鉱石の採取にあった。しかし遊牧民族特有の男系社会が生んだ「男性結社」の暴走で、「善」の宗教が形成され、インドに移動したのがインド・アーリア系で、東イラン(アフガニスタンを中心)に残ったのがイラン・アーリア系。インド・イラン系アーリア人が、まだ未分化の時代に、先住のインダス文明やインダス系の人々がオクサス河(プラアムダリアか?)のデルタ地帯に形成した農耕都市文明と接触する過程で、「アディティ」や「アナーヒター」という女系農耕社会の「自由の女神」と融合した。そして、元々遊牧民であったイラン・アーリア人は山麓で「牧畜」と「農耕」も営むことを選択し、鉱山採掘技術を生かして地下水脈・カレーズ(カナート)を掘削、インダス文明を特色づけた「水路」を山麓で確保、インド・アーリア系は「地下水脈の伝説」(サラスヴァティ)を伝承した。−ここまでが23号までに記述したことである。今回は、女系農耕都市文明と男系遊牧社会との接触が、人類史にどのような影響を与えたかについて記す。
● 「古ヨーロッパ」と「アジア」が父権的、好戦的遊牧民に侵略され始まった人類史

男系遊牧民に征服された女系「古ヨーロッパ」(右)と大女神(左)
私は、尊敬する加藤九祚先生とある時、「このペルシャ系(私はアーリア人のことをわかりやすく話題にする時時々ペルシャ系と話す)の物語は、戦後日本の歴史学会で大きな話題になった、江上波夫先生の騎馬民族征服説に似てますね」と話したことがある。特に、インドで、カースト制度を作り上げたインド・アーリア系の動向は、今日に至るまでその歴史を背負っている。私は、応神天皇以降(5世紀以降)、日本の古墳時代の出土遺物に馬具が出土したり、騎馬文化の登場することが、中国における鮮卑等の活躍と重ねて、アジア史の中でも面白い現象と考えている。この稿で記した、オクサス河以南で展開された物語は、紀元前2000年の昔に遡り、文字通り「騎馬民族征服説」は成立したと思う。最近の学界では「アーリア人による先住民の虐殺や侵略はなかったというのが通説」と声高に唱える人もいるが、「征服」は、暴虐だけでなく、融合も伴って行われるものであり、何よりも「善」の宗教が誕生したり、インドで「カースト制度」が今日まで残っていることが、「征服」の証明と考えられる。 「戦車」、そして後には騎馬を伴う牧畜民が跳梁する男性優位の社会は、黒海、カスピ海の北部から東方アルタイ山脈にかけた一大草原地帯で形成され、氷河期からヒプシサーマル期に移行し、川沿いで形成された新石器農耕文化、特に銅や金を使用し始めた農耕都市文明を襲ったことが、現代につながる人類史上の画期として注目されている。 この稿で取り上げた地域は、中央アジアから南方、イラン、インドそしてメソポタミアにかけての「アジア」であったが、西方「ヨーロッパ」でこの人類史上の画期を取上げたのが女性の考古学者マリヤ・ギンプタス氏である。「古ヨーロッパの神々」(鶴岡真由美訳、言叢社)では、黒海西方の(1)エーゲ海・中央バルカン(2)アドリア海地方(3)ドナウ川中流域(4)東バルカン(5)モルダヴィア=西ウクライナで、紀元前6500年から3500年の、新石器時代から銅(金石併用)期時代にかけて、穀物(小麦、大麦、えんどう豆等)を栽培し、家畜(羊、ヤギ、牛、豚)を飼育する半農半牧を特徴とし、独特な様式(マリヤ・ギンプタス氏は図式主義:スキーマティズムと表現)の土器や土偶を残している「古ヨーロッパ」が紹介されている。「神像の研究を通して立証されるのは、古ヨーロッパ世界は原(プロト)インド=ヨーロッパ世界ではないということ、その系譜は、男権的な近代ヨーロッパの発展には直結していないということである。〈古ヨーロッパ〉という最初期のヨーロッパ文明は、父系的要素によって荒々しく破壊されてしまい、二度と再び元通りにはならなかった。しかしながら、その遺産はヨーロッパの基礎のなかに永々と生き続け、…西洋文明といえばギリシアから説かれるのが常であり、その出発点の背後にどんな力が横たわっていたのかを自問する人は少ない。しかしヨーロッパ文明は、ギリシア時代のわずか数世紀の間に創り出されたわけではない」と総括し、「神像は、大地の力をみなぎらせ、湿地や河や女陰のように潤い、月や女性の生理のように周期的なものを表した。それはインド=ヨーロッパ的観念、つまり戦士の神や英雄、馬、武器をもって表現し、二元対立的な世界の構造(昼/夜、男/女)をなし、太陽が支配する世界観とは明らかに異なる女性的、太陰的な世界観を映し出している」「インド・ヨーロッパ文化は、前4500年から2500年頃の間にロシアの草原地帯から三度にわたって侵入した民族によってもたらされたもので、父権的で攻略的、遊牧的で可動的、好戦的文化であり、それは南と西の端を除いてほぼヨーロッパ全域に波及した」と指摘、近現代に至る人類史を再考させる問題提起を続けている。 人類史は、地球規模の気候変化、氷河期からヒプシサーマルへの移行時期に、河川沿いでの農耕を始め、「銅」の利用によって富を蓄積し都市を形成するようになると、都市のニーズに応えるように鉱石採取と搬送のネットワークが形成され、農耕社会の周辺で牧畜を営んでいた集団の間でも鉱石のニーズが生まれ、「銅」そして「青銅器」を中心とした「鉱石」をキーワードにして、女系農耕都市文化と男系牧畜文化が邂逅した。人類が知った「鉱石」の活用は、莫大な富の源泉となる一方で、男系社会による富の集積を伴う王国・帝国、それを支える男系優位の宗教の誕生、奴隷や被支配者を差別的に扱うヒエラルヒーの形成、何よりも冶金の燃料となる大規模な森林破壊が始まり、植民地帝国興亡の歴史を刻んで今日に至っている。人類史の表面的事象は、「アジア」(メソポタミア、アナトリア、イラン、インド、中央アジア;中国や日本、東南アジアとインドア大陸のほとんどは当時は「アジア」と認識されなかった)や「ヨーロッパ」における「男系牧畜民による女系農耕社会の転覆」として現れたが、その後の歴史は、あらゆる富と奴隷そして鉱石資源を集約する男系国家(都市国家、王国)と王権・国家を支える宗教の興亡、国家をになう優勢な民族やリーダー一族による国家の運営の覇権興亡の歴史を刻んで今日に至った。
● ゾロアスター教と地下水脈が人類史最初で最大の帝国誕生を促す
中央アジアからインド、イラン、メソポタミア、アナトリアからエジプトにかけた人類最初の大帝国を打ち立てたのはイラン・アーリア系のアケメネス朝ペルシャであったが、山岳地域を拠点とするこの帝国が成立した条件の一つが「地下水脈」の活用であったことは動かせないと思う。前稿では、この地下水脈技術が、鉱石ネットワークの周辺で鉱石採取に携わっていたイラン・アーリア系の人々が、鉱山技術を活かして「鉱石」の代りに「水脈」を掘り当てる手法として応用したことで誕生したこと、そしてゾロアスターの宗教革命で山麓における農耕と牧畜が奨励され、その水源として「地下水脈:カレーズ(カナート)」が応用されたことで、ゾロアスター教がウィーシュタースパ王のサポートを得て宗教として確立した可能性について触れた。「アフラマズダの一六国」の形成は、山麓での牧畜と農耕に欠かせない水脈を確保するカレーズ技術と密接にかかわったゾロアスター教の普及と表裏一体であったと想像される。先行アーリアと表現したインド・アーリアが「錫の道」を通って、北メソポタミアでフルリ人を統合してミタンニ王国を築いていたが、後発イラン・アーリアは、ゾロアスター教と地下水脈掘削技術「カレーズ」を伴い、西方への進出をしたと考えられる。既に前稿で紹介した通り、ミタンニを滅ぼした新アッシリアのサルゴン二世の頃(紀元前八世紀)には、ウラルトゥ王国から得た技術でカレーズを掘削していた。新バビロニアと組んで新アッシリアを滅ぼしたのが、イラン高原を基盤にするイラン・アーリア系のメディア王国であったが、メディア王国の首都エクバタナ(現ハマダーン)も紀元前7世紀にはカレーズで給水されていた。このメディアを反乱で滅ぼしたのが、メディア王家の娘婿で同じイラン・アーリア系のアケメネス家キュロス二世で、アケメネス朝ペルシャの首都ペルセポリスもカレーズを水源としていた(「カナートイランの地下水路」)。ダリウス一世はエジプト征服後紀元前518年、150キロ離れた村にナイルの水をカレーズで導水したほか、アケメネス朝は地下水路を掘削して灌漑をした者には五代の子孫にまで土地の耕作権を認めたことが知られるように、アケメネス朝ペルシャは、キュロス王以来、山岳地域の占める領域が大いにもかかわらず、帝国の基盤と出来た秘密は、山麓で水脈を掘り当てる「地下水脈技術」で、山岳地域でも農耕と牧畜の暮らしを確保できたことに帰一すると考える。ゾロアスター教の形成とともに、アフラマズダが創造した「一六国」は、人類史上最初で最大の帝国「アケメネス朝ペルシャ」誕生へと変貌するのである。
● 釈迦はゾロアスター教の「善思善語善行」を知っていた
インド・イラン系によって形成された宗教は、インドでは「祭祀・戦士・平民(商業、牧畜、農耕従事者)」に従事するアーリア人を支配階層とし、それ以外の被征服民、諸民族を奴隷とし差別化する社会を折りなして、さらに被征服民の信仰を吸収しながら、バラモン教からヒンズー教へとカースト制度を継承する道を進み、バラモン祭祀に反対して登場した仏教も、梵天勧請から弥勒救済にいたるまでバラモン社会に沈むように消えた。(この稿17号参照。)しかし、インドにおける仏教の誕生をみると、バラモンの差別に反対し、生老病死という現生の苦界から解脱する道として釈迦が掲げた「八正道」(正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正定)は、インドラの暴虐に反対しあるいはインドの悪神ダエーワに反対し「善思善語善行」がチンワド橋を渡り天国に行く道だと唱えたゾロアスターの「アフラマズダ教」と酷似していることを見ないわけにはいかない。ゾロアスターの啓示と普及(布教)は困難を伴い、誕生の地であるヒンズークシュ南のシースタンからアラコシアで、インダス川西方のトゥーランの人々の間での宣教に挫折し、ホラーサーンのハリーロード流域でウィシュタースパ王の教化に成功し、ゾロアスターの妻、及び娘がウィシュタースパ王の宰相及び娘との「政略結婚(?)」(伊藤義教氏)で、布教の基盤を確立したことで、東イランを中心として中央アジア(ソグディアナ)からヒンズークシュ南のアラコシアまでが、「アフラマズダが創った一六国」となった。この一六国については、釈迦が活動を展開した紀元前6世紀から5世紀の北インドの「一六王国」と「アフラマズダの一六国」との類似関係を指摘したのはゲラルド・ニョリ氏であったが、釈迦が「アフラマズダ教」を知らなかったであろうか。 既にみたように、ゾロアスター教の宇宙観のハラー山と仏教における須弥山、ハラフワティ(のちのアナーヒター)とサラスヴァティ(弁才天)、そしてアフラマズダと大日如来など、仏教的空間に透けて見えるゾロアスター教の姿は尋常のものではなく、釈迦は、ゾロアスター教の教義あるいは主張を知っていたのではないかとも思える。特に仏教が「反バラモン」からバラモン社会と融和的方向を取った大乗仏教(クシャン朝)以降、社会的にはゾロアスター教と仏教の役割は同じ道筋を取って今日に至るように思われる。それは宗教が王権の後ろ盾となる道であった。
● 国家のバックボーンとなったゾロアスター教=ユダヤ教、キリスト教、イスラム教誕生の背景
ゾロアスター教が最初に布教を拡大したのは、ゾロアスターがウィシュタースパ王を教化してからであった。 その後イラン高原で最初にイラン・アーリア人の国家を立ち上げたのはメディアであった。メディアでもゾロアスター教の祭祀が行われていたようであり、紀元前550年、メディアの娘婿であったが反乱しアケメネス朝ペルシャを立ち上げたアケメネス家のキュロスは、ゾロアスター教に従って公正に収めようと務め、またキュロスの娘にウィシュタースパ王の妃の名を与えているという。キュロスの治世で「人類の宗教史で特殊な例」(メアリー・ボイス)として注目されるのが、新バビロニアに捕虜としてエルサレムからバビロニアに連行されたユダヤ人は、キュロスがバビロニアを占領した時に開放されエルサレムに帰還する、ユダヤ人のバビロン捕囚からの解放。メアリー・ボイスは「ユダヤ人はこの(帰還)後もペルシャ人には好感を持ち続け、ゾロアスター教の影響を一層受けやすくなった・・・これら(イザヤ書)の詩句はゾロアスター教の教義と聖典に驚くほど似ており、ゾロアスター教が捕囚後のユダヤ教に及ぼした強力な影響の最初の足跡を示す」「・・・ゾロアスターの根本的な教義の多くは、次第にエジプトから黒海までの全地域に伝播するようになった。すなわち、創造主である至高神がいること・彼と対立し彼の支配下にはない悪の力が存在すること・この悪の力との戦いを助けるために、多くの下位の神々が創られたこと・この世界は目的があって創造されたこと・現状ではこの世界は終末をむかえること・この終末は宇宙の救世主が予告し、彼がその完遂を助けること・その間には天国と地獄が存在し、個々の魂には死んだ時に運命を決める個別の裁判があること・時の終わりには、死者のよみがえりと最後の審判があり、邪悪なものは消滅すること・その後神の王国が地上に来たって、正しいものは庭園(「楽土」のペルシャ語)に入るようにこの王国に入り、そこで神の前で永遠に魂と同様肉体も不死となって幸せになること、などである。これらの教義はすべて、捕囚後のユダヤ教のさまざまな学派に受け入れられるようになった」と記し、アレキサンダーの侵攻を経た後の、アルサケス朝パルチアの5世紀を通して、ゾロアスター教とユダヤ教の関係は良好で、ユダヤ教の著作には、ゾロアスタ教的思想が反映されていると指摘している。キリスト教もイスラム教も、ゾロアスター教の教義を吸収したユダヤ教の信仰的世界から形成されている。そしてこれらのすべての世界宗教は、帝国形成のバックボーとして機能してきた。
● 「アジア」「ユーラシア」は、ギリシア・ローマ帝国の子孫たちによる植民地用語
人類史は、ヘロドトスの「歴史」で記されたペルシャ戦争がのちのアレキサンダー東征の引き金となり、植民地帝国興亡の歴史が始まった。ここでヘロドトスが「歴史」で多用した「アジア」と「ヨーロッパ」および近現代使用されるようになった「アジア」と「ユーラシアについて触れておく。 ヘロドトスは「歴史」で、「・・・そもそも何故に本来一つである陸地に女の名に由来をもつ三つの名(ギリシャの周辺に存在する「アジア」、「ヨーロッパ」、「リビア」を指す)が附けられ、またエジプトの河であるナイル河、コルキスの河バシス―マイオティス湖に注ぐタナイス河(ドン河)と「キンメリア渡し」を挙げる人もある―がその境界線とされているのか、その理由は私の理解に苦しむところであり、またどういう人たちがそのような区分をしたのか、その人たちの名前も、またそれらの命名の由来も私は知ることが出来ぬのである。リビアはその地方の土着の女リビア(リュビア)にちなんだ名であると多くのギリシャ人はいっており、アジアはプロメテウスの妻の名に基づいたものという。しかしリュディア人はその名は自国のものであるといい、アジアの名称はマネスの子コテュスの子アジアスにちなんだ命名で、プロメテウスの妻のアシアの名に由ったものではない、サルディスに住む民族、アシア氏の名も同じ起源であると称している。 またヨーロッパ(エウロペ)が周囲を河海でめぐらされているかどうかは何人も知らず、その名称をどこから得たのか、その命名者が誰であるかも明らかでない。われわれとしては僅かにこの地方がその名をテュロスの女エウロペから得たことをいいうるのみである。さればヨーロッパも他の二大陸と同様、以前は無名であったに相違ない。ともかくエウロペなる女がアジアの出身であることは明らかで、この女が今日ギリシア人がヨーロッパと称している土地へ来たことはなく、せいぜいフェニキアからクレタ、クレタからリュキア迄しか行っていないことも明白である。・・・それらについてはわれわれも慣用に従う・・・」 要するに、ウクライナからロシアへの編入で揺れるクリミアのボスポロス海峡とエーゲ海とマルマラ海をつなぐヘレスポントス(チャナッカレ海峡:ダーダネルス海峡)が「ヨーロッパ」と「アジア」の境であった。アケメネス朝ペルシャはこのヘレスポントスに架橋しギリシャやスキタイを攻めた。トロイ戦争はこの海峡のアジア側で行われ、アレクサンダーの東征もこの海峡を渡り、オスマントルコの地中海覇権の拠点となったのもこの海峡、ウィンストン・チャーチルが1915年オスマントルコの首都攻撃に失敗し引責辞任したのもこの海峡での戦いであった。クリミアに黒海艦隊の基地を置き、ユーラシア大陸の東端でヴラジヴォストーク(「東方支配」の意味)を命名した艦隊が出撃したのもこの海峡だった。黒海が「ヨーロッパ」と「アジア」の境界だったのである。

しかもこの「アジア」の東端は「インド」であって「・・・われわれが多少とも確実な知識を持っている限りにおいて、アジアに住む人類のうちではインド人が最東端の民族なのである。インドの東方は砂漠をなしているため全く無人の境だからである。・・・」とヘロドトスは記し、インドでの仏教の形成や中国の動向は全く眼中になかった。しかも、ギリシア、ローマ帝国の子孫であるヨーロッパ人は16世紀の大航海時代まで、「アジア」を「アケメネス朝ペルシャ」の最大領域と考えており、ポルトガル、スペインによる植民地時代の開幕まで「アジアの東端がインド」という認識は変わらなかった。「インド」という言葉は、あくまでも「アジアの果て」という意味であり、ポルトガルの植民地開拓時代の後、貿易の権益を目的とする株式会社「東インド会社」の活動も、「ヨーロッパ」以外での、この植民地における利益独占の経済活動を目指す「アジアの果て」での貿易活動を意味した。つまり植民地時代の当初にあっては、「インド」と「アジア」はほとんど同意義であり、従って、インドネシアや西インド諸島での植民地貿易やアメリカ大陸の先住民族をインディアンと称するなどの現象も生まれた。西インド諸島からアメリカ大陸を越え、太平洋を越えて黒船が日本列島に達し、オランダに続いてイギリスやフランスが東南アジアから中国に姿を見せ、ビザンチン帝国の後継国家を自認するロシアがウラル山脈を越えて、中央アジアや中国、シベリアを越えて日本列島に達することで、中国、日本列島までが「アジア」となり、日本列島の西方の大陸の名称は「ユーラシア大陸」となった。ギリシャの昔から「アジア」はギリシャを含めた西方世界にとって植民都市が展開する植民地のことであり、15世紀末以降、「インド」の東方に新たに拡大した植民地を指す言葉となった。EURASIAN , a term originally confined to India, where for upwards of half a century it was used to denote children born of Hindu mothers and European( especially Portuguese )fathers .(エンサイクロペディア・ブリタニカに記載) そして「ユーラシア」については、ギリシア、ローマ帝国の子孫と自認する人々が、インドで現地の女性とのあいだに誕生した「ヨーロッパ」でも「インド=アジア」でもない混血児を指す言葉として生まれたのが「ユーラシアン」という言葉であったことに明らかなように、「アジア」という植民地の拡大とともに「ユーラシア」も誕生しており、「アジア」「ユーラシア」というこの二つの言葉はいずれも植民地用語そのものだと言える。逆に言うと、15世紀末までは、インド以東は「アジア」では無かったのである。
● 50億年後まで持つか、地球と人類
インドラの酩酊陶酔の末の暴虐に対する自省から生まれた「善思善語善行」のゾロアスター教は、この「アジア」で生まれ、東では仏教、マニ教、西では、キリスト教とローマ帝国の国教の位置を争ったミトラ教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教形成に影響を与え、地球上の富の集約を目指す植民地帝国のバックボーンとして国家民族興亡の歴史と共にあり、奴隷を形成し、女性や被支配民族を差別する男系優勢の社会を形成、地球生命の存亡の危機をもたらした自然資源の略奪と深刻な森林破壊の歴史を刻んできたが、皮肉にも、「善思善語善行」の宗教が誕生して以降、歴史は加速されたとも思われる。人類に未来はあるのだろうか。 最後に、地下水脈の表彰として取り上げてきたアナーヒターについて触れる。(1)アナーヒターは、ナヴルズ(春分の日)にハラー山のフカルヤ峰から地下に下り、中央洲で地上に吹き出し、アフラマズダが地の七洲にこの水を配して、農耕と牧畜を助けるアフラマズダの娘であり、アケメネス朝ペルシャのダレイオス一世の時代から記録され、(2)のちにはハラフワティ(サラスヴァティ:弁才天)やアールマティにとって代わるほどの大女神であり、創造神アフラマズダ、太陽神ミスラと並ぶゾロアスター教の象徴であり、(3)東アジアでは観音菩薩や弁才天に姿を変え、大乗仏教を支える大女神として大活躍してきたが、地上ではオクサス(アムダリア)がアナーヒターとして語られることがあり、天空では明けの明星、宵の明星として知られる「金星」を表象としている。この金星は、太陽系の地球のすぐ内側を回っているが、地球によく似た惑星として知られ、かつては水が大量にあったが蒸発し、大気中は二酸化炭素で覆われていると考えられている。金星と同様、マントルの上に薄皮一枚で浮かぶ大地に暮らす生命体の一つである人類は、46億年の地球時間のほんのわずかな時間である4千年足らずで、国家民族宗教が興亡し、侵略殺戮を繰返し、未曾有の森林破壊、自然資源を略奪し、現在地球温暖化に直面している。山−河−海(湖)と循環する自然(水)の象徴としてきたアナーヒターは、悪と戦う先頭に立って、善思善語善行を目指す人間と共にあるとされる。観音菩薩(アナーヒター)が常行する兜率天で下生を待つ弥勒(ミスラ/ミトラ)とともにある空海が、弥勒とともに救世主として地上に降りるのはこれから50億年後のことである。地球は金星と同じ運命をたどるのか、人類は地球とともに生き残れるのか、民族の共生・自然との共生という課題に打ち勝てるのか、頭を抱える昨今である。
(第二章―アジア源流「〝幻の河オクサスから世界は始まった〟という物語」完)
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。