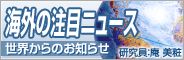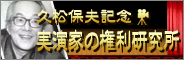「ワンチャンス主義」という名の“ゆうれい”(改定稿)
棚野正士備忘録
09.3.23(2017.12.3 一部改定) 棚野正士
★実演家の権利は「ワンチャンス主義」というあいまいな概念で捉えられて、「ワンチャンス主義」という言葉によって、それがあたかも実演家の著作隣接権の基本的な性格であるかのような誤った考え方が法律専門家の間においても存在しているように感じる。
しかし、それは実体のない“足がないゆうれい”のようなものである。
★10年以上前のことだったと思うが、「ワンチャンス主義」という言葉を取材しているときに分かったことは、この便利な言葉はローマ条約(実演家等保護条約)19条(映画に固定された実演)を指して、現行法立法時に文部省(あるいは文化庁)の著作権担当者が言い出した内部用語ではないかということである。国内法の実演家の権利に関する規定を指した言葉ではなく、映画に固定された実演についてのローマ条約の規定を指したものだと推測される。
ローマ条約19条(映画に固定された実演)は「この条約のいかなる規定にもかかわらず、実演家がその実演を影像の固定物又は影像及び音の固定物に収録することを承諾したときは、その時以降第7条(注:実演家の権利)の規定は、適用しない。」と定めている。
ローマ条約19条の性格を「ワンチャンス主義」という言葉で捉えることは、大変分かりやすく的確である。しかし、国内法の実演家の権利は、そのモデルとなったローマ条約より保護が厚く、国内法の実演家の規定まで「ワンチャンス主義」という言葉で捉えると、法的性格があいまいになるのではないだろうか。
★「ワンチャンス主義」について、「著作権事典」(出版ニュース社)は、「ワンチャンス主義とは、実演家の権利の基本的性格を説明する際に用いられる用語である。ローマ条約においては、いったん許諾を与えて実演を録音・録画すれば、その同じ目的のために録音・録画物を増製することについては実演家の権利が働かない主義をとっている(ローマ条約7,19)。」「ワンチャンス主義とは、このようにローマ条約上の実演家の権利の性格を説明するために、日本の立法関係者が便宜上使用した言葉であり、国際的に通用するものではない。」と述べている。
★著作権法で実演家の権利を考える場合、重要な規定に103条で準用する63条がある。63条1項は「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」と定め、同条2項で「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」と定めている。
この規定を103条によって、実演家に準用すると、「実演家は、他人に対し、その実演の利用を許諾することができる。」「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る実演を利用することができる。」となる。
例えば、映画の場合、上映、頒布等、映画を映画として利用する場合は、実演家が許諾した利用方法及び条件の範囲内であるが、映画を部分利用する場合は“許諾に係る利用方法条件の範囲内”の利用ではなく。“目的外の利用”であり、実演家の許諾権が働くと考えるのが当然である。実務上も、放送番組における映画の部分利用については放送事業者と協議して一定の使用料を徴収していた。PRE(映像実演権利者合同機構)事務局長であった故・平井和夫氏はこの考え方を採り、IT企業法務研究所セミナー(08.3.25「PREXの概要」)で講義した場合も、映像実演の部分利用に関する法的根拠を103条で準用する63条に求め、PREで行っている部分利用の業務の詳細を説明した。
実演家の権利と63条の関係は今後とも議論を深めるべき課題である。ワンチャンス主義というゆうれいは、その時に姿を消すだろう。
(追記)橋元四郎平先生は、「著作権情報センター発行”コピライト 1996年5月号”に”著作権人語 当世風「身分から契約へ」”を書いている。この中で橋元先生は、「我妻栄”民主主義の私法原理”」を引用し、「進歩的な社会の推移は、今までのところ、身分より契約への推移であった」と述べて、「実演家という”社会的身分”によって権利ないし法律関係が定まるのではなく」「早く”契約”の段階に進んでほしいものである」と述べている。「身分から契約へ」は実演家の根本的課題である。
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。