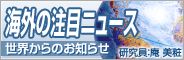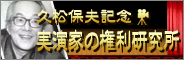著作隣接権の生成と芸能組織 ―日本の芸能組織、芸能文化団体がどのように時代の風を興してきたか―
棚野正士備忘録
IT企業法務研究所主任研究員 日本音楽事業者協会 顧問 棚野 正士
(本稿は、社団法人日本音楽事業者協会(JAME)「JAMEマネージャー養成講座2006」で私が担当した講座の記録である。なお、養成講座での演題は「CPRAを創った音事協―著作隣接権の生成と芸能組織―」。) 【資料はこちらからダウンロードできます。(PPTファイル:278KB)】 1.実演家の団体、事業者の団体、両方から見る芸能という富士山 初めのスライドに富士山が出ていますけれども、これはお風呂屋さんの真似をしたわけではなく、わたくしの想いとしてはこういうことであります。現在の著作権法は昭和45年(1970)にできたんですが、それがきっかけになって、わたくしは社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)に入り、30年間著作権法にかかわる仕事をしてまいりました。 そこでは、実演家の立場から芸能文化を見てまいりましたが、平成14年(2002)に芸団協を退職し、現在はIT企業法務研究所(LAIT)で知的財産全体を勉強しております。そして昨年・2005年春からはLAITの立場で音事協特別顧問の役目を頂戴し、こんどは事業者の立場から芸能産業を勉強しております。まだまだ研修中ではありますが、かつては実演家の立場から芸能という富士山を見てまいり、今度は事業者の立場から同じ富士山を見ようとしております。両方から眺めて初めて芸能という富士山が分かってくるように思うのです。 2.実演家=実演者(自然人)+事業者(法人) 30年間、実演家の団体の中で、実演家に夢を託しつつ実演家の問題を考えてまいりまして、「実演家」に対するわたくしのイメージを申し上げますと、自然人である実演者イコール実演家ではなく、自然人である実演者に協力するマネージャーあるいは事業者がいて初めて実演家が成立しているように思います。 すなわち、実演家は実演者本人と事業者の両者によって形成されているように思われます。 しかし、そうは言うものの著作権法の枠組にはマネージャーあるいは事業者は入っておりません。実演に関しては、実演家が規定されているだけです。 3.著作権法の枠組―美空ひばりさんに見る実演家の特性― 著作権法という建物は「著作権」という階と「著作隣接権」という階に分かれています。「著作権」の階は著作者の権利について定め、「著作隣接権」の階は実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の4者の権利を定めています。この4者は「著作物を伝達する者として保護する」ということが法の趣旨ですが、4者の中で、実演家は他の3者とは立場が違うだろうと思います。 例えば、音楽の著作物の場合、楽譜は音を出しません。演奏家あるいは歌手によって初めて音楽の作品が出来上がるのです。実演家は著作物を伝達するというより、むしろ創作する者であるといえます。かつて、作詞家の石本美由紀さんが美空ひばりさんについて、「美空ひばりは作家が思うとおりの世界を描き出してくれるというより、考えもしなかった世界を描きだしてくれた。」と歌手論を述べていました。これは美空ひばりさんという天才の話ではありますが、実演家の特性を言い当てていると思います。 その意味で、実演家は作家に近い、著作者に近いと言えましょう。著作権法の歴史を見ると、実演家の権利は著作者の権利に近づく歴史であると言えます。今、IPマルチキャスト放送を巡って、実演家の権利を引き下げようという方向ですが、法の歴史を見ると、実演家は著作者の権利に近づいていく方向であり、引き下げは歴史に逆行するように思います。 4.枠組の見直しー実演家の権利と事業者の権利― 著作権法は著作権制度と著作隣接権制度の二つに分かれ、著作権制度は「著作者の権利」を定め、「著作隣接権制度」は「実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利」を定めていますが、著作隣接権4者の中で、実演家だけが自然人で他は事業者です。又、実演家は創作者に近い立場ですが、他は著作物の伝達者です。 このことを考えると、著作権法という建物は「著作者の権利」「実演家の権利」「事業者の権利」と三つの階に分けて理解した方が良いように思います。 そして、「事業者の権利」の階には、出版者の権利や集団実演における理事会の権利、経営者の権利、主催者の権利、あるいはプロダクションの権利も置くことが検討されることになるかも知れません。 5.ドイツ著作権法に見る事業者の立場 ドイツ著作権法(1965年9月5日著作権及び著作隣接権に関する法律)(斉藤博訳・CRIC外国著作権法令集16)を見ると、日本の著作権法にはない注目したい条文があります。 第79条(労働ないし雇用関係にある実演家)、第80条(合唱、オーケストラ演奏及び舞台の上演)、第81条(開催者の権利)です。 これらの規定は、もしかして日本の著作権法で事業者あるいは経営者、主催者の権利を考える場合に何らかの示唆を与えるかも知れません。(資料参照) 6.浪曲に始まる実演家の権利 本マネージャー養成講座第1回で、堀威夫元理事長が「近代プロダクションの歴史」と題して名講義をされ、その中で、「プロダクションの歴史は浪曲から始まる」と話されましたが、実演家の権利も又浪曲から始まります。 旧著作権法は明治32年(1899)に出来ましたが、大正9年(1920)の法改正が実演家にとって大変重要です。明治の終わりから大正の初めにかけて浪曲師・桃中軒雲右衛門の浪花節レコードの海賊版が出まして訴訟になりました。一審、二審では勝ったのですが、大審院で負けてしまいました。このため議員提案で著作権法が改正され、保護される著作物に「演奏・歌唱」が追加されました。 大正9年帝国議会衆議院小委員会で、提案者鳩山一郎衆議院議員は「天才と熟練とによって初めてなされることを得べき演奏を、原著作者と異りたる一つの芸術と認めることにおいてどういう不都合があるでありましょうか。」と演 説しています。実演家(当時は著作者)の性格を良く言い表わしています。 このように、旧著作権法では、日本の実演家は著作者だったという世界的に見ても特異な歴史があるのです。 7.旧著作権法の大改正と実演家の大運動 昭和37年(1962)に旧著作権法の大改正作業が始まりました。この政府による改正作業を受けて、当時の俳優の団体、演奏家の団体が大同団結して日本芸能実演家団体協議会(芸団協)を結成して、新しい著作権法に実演家の権利を書き込むために大運動を起こしました。昭和40年(1965)のことです。 この時実演家の権利のモデルにした国際ルールが1961年にできた「ローマ条約」(正式名称は「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」―当時は「隣接権条約」と呼ばれ、今は「実演家等保護条約」と略称されている。「ローマ条約」は国際的な通称―)です。ローマ条約は実演家だけでなく、レコード製作者、放送事業者の権利のモデルでもあります。 8.実演家の権利のモデルとなったローマ条約 ローマ条約は1961年にローマで開かれた外交会議で作成されましたが、この条約ができたきっかけについて、WIPO(世界知的所有権機関)の解説書はこう述べています。 「彼ら(実演家、レコード製作者、放送事業者)が保護を享受すべきかどうかの問題は、長い間討議され、また、関係当事者を代表する多くの団体の一大関心事であった。いずれの出来事が他に先んじたかは、はっきりしない。今世紀の初めから多くの研究が行われ、示唆が提起され、また立場が表明された。その多くの中の一例は、国際文芸美術協会(ALAI)が、1903年にワイマールで開催された総会において、ソロの実演家の苦境に同情を示したことである。」(著作権資料協会発行・大山幸房訳WIPO「隣接権条約・レコード条約解説」9ページ) “実演家の苦境”というのは、放送、レコードあるいは映画などの新しい技術が進むようになって演奏家、実演家が生の実演の機会を喪失してしまうことを指しています。“機械的失業、技術的失業”(technological unemployment)という問題です。 このように、実演家の権利は元々実演家の労働問題がきっかけになっています。このため初めはILO(国際労働機関)で論じられました。そして、長い論議と共に労働問題から著作権的な問題に発展して、やがて60年の年月を経てローマ条約として実を結んだという歴史です。 9.ローマ条約の大切な条文「レコードの二次使用」 実演家にとっていちばん大切なローマ条約の規定は、「第12条(レコードの二次使用)」です。 商業用レコードが「放送又は公衆への伝達に直接使用された場合には、単一の衡平な報酬が、使用者により実演家若しくはレコード製作者又はその双方に支払われる。」と定めています。 この条文について、先程のWIPO条約解説は次のように述べています。 「条約が定めていないもう一つの重大問題がある。それは、実演家に支払われるべき報酬は、各個人に分配するか、又は実演家の団体に渡して実演家全体の利益のために共通の若しくは社会的目的に使用することができるかである。」「二次使用は実演家全体に損害を与えるのであるから、もっぱら補償の問題であるということを根拠にして、加盟国が個人の権利を無視して、集団制度(collective system)を設けることを条文上禁止していない。この見解をとるならば、相互援助基金を設けることができる。このような解決策は、特に開発途上国において、地域の芸術家にとっての助けとなりうる。」(前述WIPO解説70ページ) 10.ローマ条約を引き継いだ著作権法の「レコード二次使用料」 旧著作権法は昭和45年(1970)に改正されて今の著作権法が生まれました。著作隣接権制度はローマ条約をモデルにして創られました。 実演家の重要な権利であるレコード二次使用料については、“レコードの二次使用によって当該実演家のみならず他の実演家の実演の機会が失われるといういわゆる機械的失業に対し、実演家全体に補償するという趣旨によって設けられたものである。”という立法趣旨に基づいて制度がつくられました。 このため、レコード二次使用料は個人に分配せず、団体で扱う団体方式がとられました。そして、著作権法で、「二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によってのみ行使することができる。」(第95条5項)と定め、社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)を昭和46年(1971)に指定しました。 11.機械的失業と芸団協 レコード二次使用料を受ける団体として芸団協を指定した文化庁は、機械的失業に対する実演家全体への補償という立法趣旨に基づき次の通り指導しました。 「二次使用料を受ける権利は、法律構成上は、実演が固定されている商業用レコードの二次使用について、当該実演家に認められる権利となっているが、本来この制度は、レコードの二使用による経済的利益の一部を当該実演家に享有させるとともに、レコードの二次使用によって、当該実演家のみならず他の実演家の実演の機会が失われるといういわゆる機械的失業に対し、実演家全体に補償するという趣旨によって設けられたものである。」 「1.各会員団体が配分を受けた二次使用料は、当該団体における新人の育成、実演の機会を失った実演家に対する保障、芸術活動の振興等のために用いるものとする。2.各会員団体は、芸団協と協議して、二次使用料のうち一定額を全国芸能活動の推進と全国芸能実演家の地位向上のための資金として芸団協に拠出するものとする。」 この指導要領に従って、芸団協はレコード二次使用料を個人に分配しないで、団体方式で取扱いました。 なお、当時、芸団協はレコード二次使用料の他、日本の実演家の統括的組織として、NHKと「実演の再利用に関する契約」「リピート放送料に関する覚書」、民放連と「テレビ放送(ラジオ放送)に関する基本協定書」等の基本的取り決めをしています。これらの基本的な契約は、それまで法的秩序のなかった芸能界に著作権法上の権利に基づいて法的秩序をつくるという役目を果たしました。 例えば、リピート放送、ネット放送の場合、出演料に一定の料率を掛けて実演家の報酬とするという方式です。そして、出演時の契約で、芸団協基準を下回る場合は芸団協基準が適用され、上回る場合はその取り決めが効力を持つというルールです。そして、報酬は芸団協を通さないで、放送事業者から直接実演家あるいは代理人に支払われます。 実演家の権利の歴史を振り返ると、日本の俳優、演奏家等の実演家は大同団結して著作権法の大改正を機に大運動を起こし、法律ができると、今度はその権利を実現するために契約や協定を次々取り交わしてきました。例えば、平成4年(1992)3月現在では、国内の契約、海外との協定等合わせて78件の取り決めがありました。 12.実演家の権利を取り巻く状況の変化 ―意識の変化と技術の変化― 著作権法が生まれた1970年代から20年経って1990年代になりますと、実演家の権利を取り巻く状況は大きく変化します。 例えば、レコード二次使用料の場合、実演家全体に補償するという機械的失業への補償という社会法的な考え方から、権利者の財産権を管理するという私権の原則に回帰していきます。分配も、個別分配しないで包括的に使用するという方式から個別分配を基本にするという方式に変わっていきます。個別分配を基本にして、権利者の合意の下に団体に拠出し、あるいは共通目的に使用するというやり方に変化します。 そうした変化の背景には、使用額が個別分配が可能となる程度に増えてきたこと、又、個別分配するためのデータ整備が出来てきたという状況の変化があります。技術環境もアナログ環境からデジタル環境に変化しました。 さらに、法的権利も貸レコードに関する権利、私的録音録画補償金、送信可能化権等と拡大してきました。 13.実演家著作隣接権センター(CPRA)の発想 ―CPRAは専門病院― 昭和37年(1962)から始まった著作権法の大改正作業を契機に生まれた芸団協は、事業としては、著作権法の実演家の権利の管理業務を中心に、芸能実演家に関する調査研究、新人の育成・技術向上のための研修会、公演および講演会の開催、福祉事業等を行ってきました。 著作権法に関する業務は昭和46年(1971)に商業用レコード二次使用料、昭和60年(1985)に貸レコード業務について文化庁の指定団体になっており、私的録音録画補償金業務については指定団体に準じる業務を行っています(私的録音は平成5年(1993)、私的録画は平成11年(1999)から)。 このように、芸団協は多目的事業を行う法人です。多目的事業を総合的に行うことで実演家の利益を計ってきましたが、執行機関としては理事会一つです。事業ごとに委員会があり、各委員会に執行の一部(場合によっては全部)を委任できるとはいえ、それぞれの事業が拡大してくると、理事会だけで事業を行うのは困難になります。場合によっては、組織上の執行責任が不明確なまま事業が遂行されるおそれが出てきます。 このようなことは、他人の権利の委託を受けて行う業務で許されません。権利者の財産権を扱うことは重大な責任を伴うという認識に立たなければこの業務は成立しません。この場合、権利に関する業務の基本的視点は「団体」ではなく「委託者たる権利者」です。そして、他人の権利を扱う業務といった場合、その「業務」とは何か。それは使用料・報酬の「徴収と分配」です。 このような考え方で、CPRAを発想しました。端的に言えば、CPRAは専門病院であるという発想です。一つの法人の中にあるが、理事会が業務を行うのではなく、専門医を集めて専門家によって独立的に運営されるという考え方です。 14.CPRAの成立 CPRAは平成2年(1990)に発想しまして、平成5年(1993)に発足しました。この間、日本音楽事業者協会、音楽制作者連盟等とはかなり協議を重ねました。音事協、音制連は芸団協という社団法人の外にいる団体ですので何回も何回も議論をいたしました。 論議の一つは、芸団協の中に置くか、独立的に外につくるかという問題です。これは大問題でしたが、最後は音事協の決断で芸団協という社団法人の中にCPRAをつくりました。 平成5年(1993)に発足したCPRAは平成10年(1998)に見直しました。見直しに際して“法人内法人をつくる”という一見訳の分からないような、しかし分かるような考え方を取り入れました。それはこういうことです。 社団法人の場合、最高意思決定機関として「総会」があり、執行機関として「理事会」があります。わたくしは、一つの法人の中に、これを二重につくるという構想をいたしました。 そして、最高意思決定機関として「顧問会議」を置きました。顧問会議が社団法人の「総会」に当たります。顧問会議は芸団協会長の職にある者、音事協会長の職にある者、音制連理事長の職にある者、議長は芸団協会長とするということにしまして、顧問会議が重要事項を決定する構造です。 又、理事会に相当する機関として、運営委員会を置きました。芸団協に理事会がありますが、著作隣接権に関しては、すべて運営委員会が執行していく、運営委員会が執行責任を負うという構造です。そして、事務局も区分して置く、というやり方です。 15.CPRAの狙い 平成11年(1999)5月27日、参議院文教・科学委員会で著作権法改正が審議された時、参考人として呼ばれまして、映画問題について意見を述べるとともに、CPRAに関する質問にわたくしは次の通り答えました。(「実演家著作隣接権センター(CPRA)設置とその背景」―著作権情報センター発行「コピライト」1997.7−ご参照下さい。) 「実演家著作隣接権センターを、関係団体の協力を得まして昨年(1998)再構築しました。関係団体というのは、現在の芸団協の正会員団体、59団体6万4000人以外の関係団体、具体的な名前を申し上げますと、日本音楽事業者協会、音楽制作者連盟、事業者あるいは制作者といった実演家のパートナーたちの協力も得て隣接権センターを再構築したということを申し上げたいと思います。 そういう意味では、従来は社団法人芸団協内の隣接権センターでありましたけれども、今後は、法人芸団協の中にありますけれども、日本の隣接権センター、しかも内容的には世界最強のものにしたい。隣接権処理、実演家の権利処理はヨーロッパにおいてもまだまだ発展途上でございまして、隣接権処理のシステムを日本としてはむしろ発信したい、輸出したいというぐらいの意気込みであります。」(第145回国会参議院文教・科学委員会会議録第13号15ページ) なお、同委員会は6月1日、著作権法改正法案可決に際して、実演家の人格権及び視聴覚実演に関する権利について付帯決議を全会一致で採択しています。 16.CPRAの基本理念 CPRAは権利者の権利の管理について、団体主義から私的財産権管理の基本思想へ回帰するという姿勢でつくられました。考え方は単純明解です。それは、 ●各人の物は各人の元へ ●権利者の物は権利者の元へ ということです。又、CPR運営の基本理念も単純明解です。 ●独立性 ●専門性 ●透明性 権利者の委託を受けて財産権を管理するためには、明確な責任体制に立って権利者との間に高度の信頼関係を築くことが必要です。そのためには、独立性、専門性、透明性が重要です。なぜなら、CPRAは「専門家による専門病院」ですから。 なお、社団法人日本芸能実演家団体協議会は、独立性のあるCPRAを組織内に位置づけるため、定款の改正を平成13年(2001)に行いました。 [実演家の権利雑感(1):法解釈の怪しさとその背景] 1.ワンチャンス主義というユウレイ 実演家の権利に関して、「ワンチャンス主義」ということが言われます。いったん許諾を与えて実演を録音・録画すれば以後権利を失い、以後の利益を確保するためには当初の契約で利益を確保しておかなければならないというような意味で使われます。この言葉は実演家の権利を否定的に言う場合に良く持ち出されます。“実演家はワンチャンス主義だから、最初に契約で決めてなければ権利はないよ!”というように。 しかし、これは間違いではないかと思います。わたくしは著作権事典で「ワンチャンス主義」を担当したとき、多くの人に取材しました。結果から言いますと、この言葉は、ローマ条約の実演家の権利の性格を説明するために、政府の著作権担当者が言い出した便宜的な部内用語ではないかという事です。法律用語でもないし国際的に通用する言葉でもありません。ローマ条約上の実演家の権利は確かにワンチャンス主義です。しかし、日本の著作権法はローマ条約より厚い保護を実演家に与えています。 例えば、劇場用映画を考えて見ましょう。よく「実演家の権利はワンチャンス主義だから、映画に録音録画されると以後権利はない。」と言われます。ほんとにそうでしょうか。 著作権法の中に大変重要な規定があります。第63条(著作物の利用の許諾)です。これ以外忘れてもよい位大切な規定だとわたくしは思っています。 「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。その許諾を得た者は、その許諾の利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」と書いてあります。 第63条は実演家に準用されています。準用して読み替えますと、 「実演家は、他人に対し、その実演の利用を許諾することができる。その許諾を得た者は、その許諾の利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る実演を利用することができる。」 この条文を当てはめますと、実演家が劇場用映画に出演した場合、映画が映画として利用されることについては、実演家は当然了解しなければならないと考えます。例えば、劇場で上映する、放送で放送する、あるいはDVDにする等の場合は、映画を映画として利用することに当たります。 しかし、劇場用映画を部分的に利用した場合、例えば放送で映画の一部を使うとか、CMで利用するとか、又カラオケの映像に部分的に使うとかの場合は、劇場用映画の「目的外利用」ではないかと思います。映画を映画として利用することには当たりません。映画の目的外利用については、実演家の許諾権が働くと考えます。従って、放送利用の場合には、放送局が実演家に使用料を支払うということになります。払うのは実演を利用した方ですから、映画製作者ではなく放送事業者です。 それから製作会社が製作したテレビ用映画の場合、テレビ用に製作したのですから、第63条から言いますと、例えばDVDにするなどの時は、又別であると思います。 こういう問題が起きないように、制作者からも実演家からも、最初に契約をすることが大変重要であると考えます。 「ワンチャンス主義」というユウレイをなくすのは、著作権法第63条の規定ではないかと思っております。 2.iPod私的録音録画問題でのすり替え iPodの私的録音録画問題が新聞を賑わしています。著作権法で私的録音録画補償金制度を定めています。 個人的に又は家庭内その他これに準じる範囲内で著作物、実演を録音、録画するのは自由にできます。ただし、一定の場合に補償金を支払わなければならない。それは、どういう場合かといいますと、政令で定めたデジタル方式の機器で、かつ政令で定めたデジタル方式の記録媒体に録音、録画する場合には利用者が補償金を支払わなければならないと決められています。ユーザーが支払い義務を負います。 しかし、実際にはユーザーに代わって機器、機材のメーカーが支払いについて協力義務を負います。今、DCCとかMDとか、いくつかの機器、記録媒体が政令指定されています。昨年(2005年)、iPodが出てきまして、文化庁は「iPodも政令指定する」と言っておりましたが、結果的にはそうならなくて、審議会でさらに検討を継続することになっています。 なぜ政令指定できなかったかと言いますと、著作権法では、「政令で定めた機器で、政令で定めた記録媒体に録音又は録画を行う者は相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない」と書いてあり、iPodの場合は、機器と記録媒体が一体になった内蔵型であり、機器と機材を別々に捉えている今の法律では政令指定の対象として読み取ることは出来ないというわけです。 しかし、機器と記録媒体を別々に政令指定したのは、両方が一体となって使われるからこそ別々に指定したのです。又、法律が出来た当時は一体型はなかったものですから、一体型、内蔵型が出てくれば、当然それは今の法律の中で読むべきだろうと思います。 神様を拝む場合、政令指定した右手と政令指定した左手を合わせて拝むと言っても、最初から一体にして拝むと言っても、それは同じだと思います。 私的録音録画問題の背景には、何時もメーカーの反対があるように考えます。法律の構造としては、私的録音録画補償金の支払い義務者はユーザーであり、メーカーはユーザーの支払いに協力する協力義務者です。メーカーからしますと、「メーカーは協力義務者であり、当事者は支払い義務を負うユーザーである」ということです。 ヨーロッパの場合は、基本的にすべてメーカーが支払い義務者です。1965年西ドイツからこの方式が始まっておりますが、考え方は、機器あるいは記録媒体を製造し販売すること自体が著作物、実演の利用であり、ユーザーとともに共同責任を負うということにあると思います。著作物、実演の「利用者」が支払うという原則に立ちますと、ユーザーも利用者であり、メーカーも利用者であるということです。そうすると、ユーザーも支払い、メーカーも支払うということが当然でありまして、メーカーは決して部外者的な協力義務者ではなく、この問題の将に当事者であります。 こうした視点から、私的録音録画問題が早く解決してほしいと思います。 3.有線放送における目くらまし 今、IPマルチキャスト放送が話題になっています。これについて、6月20日(2006年)に文化庁の審議会の報告書が出て、パブリック・コメントを求めております。この報告書を見ますと、二つのことが問題です。一つは、「有線放送における放送の同時再送信」の問題で、これについて、「実演家に報酬請求権を与える」と書いてあります。 文化庁の資料を見ますと、現在の著作権法では、有線放送における放送の同時再送信について、実演家は「権利なし」と書いてあります。現状では権利がないが、法改正して報酬請求権を与えると報告書は言っています。 これは少し違うのではないか。著作権法の条文上、確かに実演家は「権利なし」です。しかし、立法趣旨は、実演家は放送事業者の権利を通して権利を確保するというもので、決して実演家の権利を否定したものではなく、実質的には実演家の権利を認めております。条文の文言の上では、有線放送による放送の同時再送信については、実演家の権利(有線放送権)は適用されませんが、実体的には権利が認められていますので、実演家は放送事業者に対して、放送を有線で同時再送信することについて、「NO!」と言えるのです。 放送の有線による同時再送信に関しては、著作権利者5団体とCATV事業者との間に昭和48年(1973)から包括的な契約が結ばれています。著作者4団体(JASRACと文芸3団体)は許諾権をもっていますので、“許諾して使用料”を受けます。実演家の団体(芸団協)は“放送事業者に異議を申し立てないことを約束して補償金”を受けるという契約です。なお、放送事業者は許諾権をもっていますが、“有線放送事業者が著作者と実演家の権利処理をする”ことを条件に無償で許諾しています。 この5団体契約は、著作権審議会等々で永年公的にも評価を受けてきましたが、何年か前に訴訟になりまして、芸団協は一審で負けましたが、昨年(2005)8月30日付け知財高裁判決で逆転勝訴しました。CATV側が上告して、今最高裁の決定を待っている状況です。(注:平成18年(2006)10月10日、最高裁判所の「上告審として受理しない」という決定が出て、知財高裁での芸団協の逆転勝訴が確定した。著作権情報センター発行「コピライト」No.539 3/2006 梅田康宏「判例研究」参照。) このような歴史を考えると、現在法改正が予定されている「放送の有線放送による同時再送信」は“報酬請求権”ではなく“許諾権”にすべきだと思います。 しかし、どうしても報酬請求権にするならば、「契約に別段の定めがある場合は除く」あるいは「契約に別段の定めがない限り」という文言を入れてほしいと思います。 リピート放送あるいはネット放送は実演家の許諾はなくても、放送事業者は放送できますが、著作権法には「契約に別段の定めがない限り、放送することができる」と書いてあります。又、実演家がいったん放送を許諾しますと、放送事業者が放送のために録音、録画することは実演家の許諾なく自由に出来ますが、この場合も、「契約に別段の定めがある場合は、この限りでない」と定められています。 「契約」について法律に定める事はたいへん大切です。 もう一つ「有線放送における目くらまし」に、「IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信は有線放送と同じ扱いにして“報酬請求権”にする」という問題があります。 わたくしは、これはいかにもおかしいのではないかと思います。現在、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信は実演家に“許諾権”があります。文化庁の資料にも、そのようにはっきり書いてあります。それを何故報酬請求権に引き下げるのかという疑問です。 実演家の権利の歴史、あるいは著作権法の権利の歴史を見ると、権利のないものに権利を与える、報酬請求権を許諾権に引き上げるなど上の方向に法律を変えていくのが普通だと思います。それなのに、「現行法で許諾権がある」と認めながら、何故切り下げるのか。これは“知的財産立国”という時代の流れに逆らう流れではないかと思うのです。 [実演家の権利雑感(2):45年間実演家の喉に刺さった小骨―映画の問題―] 1.1961年ローマ条約以来の課題 1961年ローマ条約成立以来45年経って未だに解決していない実演家の課題に“映画問題”があります。 ローマ条約第19条(映画に固定された実演)は、「実演家がその実演を影像の固定物又は影像及び音の固定物に収録することを承諾したときは、その時以後実演家の権利は、適用しない。」と定めています。 WIPOの図書館で当時の資料を見ると、「アメリカの主張で19条が生まれた」と書いてあります。映画について実演家に権利を与えないというアメリカの主張は40年経って未だ続いています。 映画についての実演家の権利を見直そうという動きは、1993年頃からWIPOで始まりました。2000年12月には「WIPO視聴覚的実演の保護に関する外交会議」が開かれ、本当は、実演家の権利に関するローマ条約を書き換え、新たな国際ルールが出来る筈でした。2週間、ジュネーヴで徹夜会議が行われましたが、結局はアメリカの反対で、実演家の喉に1961年以来刺さっている小骨はもう少しの所で取り出せずに条約は先送りになりました。 外交会議では、19条項については合意が得られたのですが、たった1条項についてEUとアメリカの対立が解けず問題は見送りになりました。 映画の実演に関する国際ルールをどうつくるかが、世界の実演家にとって最大の課題です。(「WIPO視聴覚的実演条約を巡るジュネーヴの二週間―人の権利か企業者の権利か」―ぎょうせい発行「文化庁月報」2001.3−ご参照下さい。) 映画に関する実演家の問題は、国際条約の問題であり、同時に日本の国内問題でもあります。日本の著作権法の実演家の権利は、ローマ条約をモデルにしていますので、映画の実演については、実演家の権利は基本的には落ちています(ただし、先に述べたように、映画の目的外利用等の場合は別です)。 映画については、条約上の問題、国内法の問題がありますが、もう一つ権利の管理態勢をどうつくるかという実務的な基盤整備の問題があります。国内法を改正するためには、CPRA等の基盤整備を確たるものにしないといけません。 実演家の権利を拡充するためには、国際条約、国内法、実務基盤整備、この三点セットで運動しなければいけません。 2.実演家の権利のための運動力学 映画の問題もそうですが、法律上の実演家の権利を拡充するためには団体としての運動力学があるように感じます。 まず問題の発見、掘り起こしが必要です。誰かがやってくれるわけではなく、それは権利者の団体の役割です。そして、その問題を行政府、立法府、学会、マスコミ等々に提起しなければなりません。何もしなければ何も起きないのです。 運動は大きい声を出さないと聞こえません。大きく動かないと見えません。そのためには、他の団体等との共同作業や国際的な連携が大切です。又、運動をするだけではなく、製作者など実演の利用者等々と話し合い、協議し、実体をつくりあげていくことも重要です。法律上の権利を拡充する場合、必ず利害が相反する立場が存在します。そのため、対立する立場の人たちと話し合い、協議し、お互いに納得して法制度をつくり上げていくことが重要です。それは自分たちでやらなければ誰もやってくれません。 法律は一日では出来ません。例えば、私的録音録画補償金制度は、権利者が政府に問題提起し、懸命の運動をして15年かかりました。ローマ条約への日本の加入も、実演家が世界の実演家の応援を得ながら運動して、10年かかりました。実演家の人格権は40年の月日を要し、最初に問題を提起し運動した俳優たちは皆んな亡くなっています。 長い時間がかかるので、誰かがやるまで放って置こうという姿勢では、いつまで経っても問題は解けません。権利拡充の運動は植林に似ています。自分の世代には間に合わなくても、次の世代のために。苗木を植えておかなければならないのです。 なお、運動によって法律で権利が拡充した場合、その権利を絵に描いた餅にしないため契約(特に団体的契約)を確立することが必要です。法律は出来ただけで放って置いては役に立ちません。法律を生かすためには契約が大切です。 [実演家の権利雑感(3):時代の風は全体としてはフォローか] 実演家の権利ということから見ますと、強いアゲインストの風が要所要所で吹いていますが、しかし、全体としては緩やかなフォローだと感じます。 今、「知的財産立国」が国家戦略です。平成14年(2002)には知的財産基本法が成立、翌年には知的財産戦略本部が発足しました。その年、知的財産推進計画2003(「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」)が出され、以後毎年公表されています。 知的財産推進計画2006を見ますと、2006年から2008年の目標を「世界最先端の知的財産立国を目指す」としています。 又、重点事項として、1.国際的な展開 2.地域への展開及び中小・ベンチャー企業の支援 3.大学等における知財の創造と産学連携の推進 4.コンテンツの振興 5.日本ブランドの振興 6.知財人材の確保・育成 他を掲げています。 さらに、具体的計画を見ますと、プロダクション・ビジネスにとって事業の参考になるものがたくさん含まれています。 エンタテインメント・ビジネス、プロダクション・ビジネスが今後の知財戦略の一つになるように思います。 そういう意味で、マネージャーの方々の活動が、今後の日本の知的財産立国の流れをつくって行かれると信じます。 皆さんは知的財産立国という国家戦略を背負っておられます。ご活躍を期待し、又、楽しみにしております。
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。