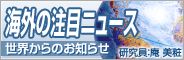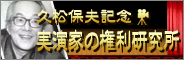俳優等が仕上げなければならない視聴覚的実演の課題 −WIPO常設委員会の検討に寄せて−
棚野正士備忘録
(コピライト1998.12掲載) 棚野 正士
● WPPTプロトコル検討への3つの道
「WIPO実演・レコード条約(WPPT)」付属条約となる「視聴覚的実演に関する議定書」についてWIPO専門家委員会が2回(1997年9月、1998年6月)開かれた後、1998年11月には、著作権・著作隣接権常設委員会が開催された。11月2日から10日まで開かれた会合では、「視聴覚的実演に関する実演家の権利の保護」「データベースの保護」「放送事業者の権利の保護」が検討されている。 視聴覚的実演に関する議定書(プロトコル)についてのこれまでの検討の経過を見ると、大きくは3つのアプローチがあると思われる。それは、「権利者保護の原則としてのプロトコル」「産業保護の手段としてのプロトコル」「政治的妥協としてのプロトコル」とでも言うべき議論である。
(1)原則としてのプロトコル 「権利者保護の原則としてのプロトコル」はECとその加盟国等の考え方である。1998年11月の常設委員会(以下、常設委員会はこの時の会合をいう)の一般討議の中で、EC代表は次のとおり述べている(WIPO報告書「SCCR/1/9.Prov.1」para.21から)。 「議定書の主目的は、すでに保護を受けている製作者ではなく、視聴覚的実演家の保護を改善し、近代化することである。ローマ条約は時代遅れになっており、保護水準はWPPTの水準に合わせるべきである。その主な目的は、聴覚的実演と視聴覚的実演に差別を持ち込まないようにしながらも、両部門の違いに当然の考慮を払い、世界のすべての国の議定書参加を確保する措置を講じ、ローマ条約の限定された受け入れ状況を改善することでなければならない。したがって、それは野心的過ぎてはならず、内国民待遇や権利の移転など、すでに解決済みの問題に変更を加えてはならない。」 そうした考え方に基づいてECとその加盟国は、固定されていない視聴覚的実演に関して、WPPT第5条(人格権)および第6条(固定されていない実演に関する実演家の財産的権利)準用を提案している。また視聴覚的固定物の利用に関してはWPPT第5条(人格権)、第7条(複製権)、第8条(頒布権)、第9条(商業的貸与権)、第10条(利用可能にする権利)の準用を提案している。(注:1.提案の注釈で「視聴覚的実演家の人格権保護の適用の範囲および方法については、さらなる検討が必要である」と記している。2.放送および公衆への伝達に関しては提案はない)。内国民待遇に関しても、WPPT第4条(内国民待遇)の準用を提案している。
(2)手段としてのプロトコル 「産業保護の手段としてのプロトコル」とでも言うべき考え方をとるのはアメリカである。アメリカ代表は常設委員会の「条約の表題と性格」検討の中で次のとおり述べた(WIPO報告書「SCCR/1/9.Prov.1」para.24から)。 「アメリカは独自条約を選択する。視聴覚的実演に対する権利に関する法的文書は、視聴覚産業における労働・業界慣行に対応すべきであるとの立場を説明した。雇用条件、契約上の取極、必要な投資の規模は、視聴覚産業に関わる人々の数とともに、音楽産業とは異なっており、したがって、別途の考慮を必要とする権利の移転に関する条項については、代表は、ローマ条約第19条と同様、ベルヌ条約においても、その第14条の2で、視聴覚著作物の利用を容易にするため、視聴覚著作物への特別な言及がなされていることを指摘した。アメリカ提案はこれらを参考としているが、実演家に対する保護を強化している。すなわち、同提案には単純な権利の推定譲渡が含まれているが、契約上の取極によって、推定譲渡に対し、反論する機会を実演家に与えているからである。」 アメリカは、人格権について提案すると共に、固定されていない実演について放送および公衆への伝達に関する排他的権利(既に放送又は公衆に伝達された実演を除く)および固定する排他的権利を提案し、固定された実演については、複製権、頒布権、利用可能化権、放送および公衆への伝達権(ベルヌ条約第11条の2の視聴覚著作物について許容される権利の行使の条件を除く。また、既に放送又は公衆に伝達された実演を除く)を提案している。しかし、一方提案では、追加的規定として、権利の移転(「実演家がその実演を視聴覚著作物に固定することにいったん同意した場合には、書面による契約に反対の定めがない限り、この条約に基づく実演家の排他的権利は、当該著作物について、その著作物の製作者およびその権利の継承人に移転したものとみなす。前段の規定は、締約国の法律に基づき実演家が享有する報酬請求権に適用されるものではなく、また、締約国に対してそのような報酬請求権の創設を求めるものでもない。」)を提起している。 また、内国民待遇に関しては、「実演家は他の締約国において、この条約において特に与える権利とともに、その国の法律が自国民に現在与えており又は将来与えることがある待遇を享有する。」と提案している。 アメリカは実演家の権利の保護というよりも産業保護の手段としてプロトコルを考えているように思われる。 アメリカにおいては実体的にみると労働協約によって実演家の利益が守られている。例えば、映画俳優組合(SAG)の団体協約がある。これは、1959年にロナルド・レーガンが委員長のときに7週間のストライキの結果生まれた契約である。キティー・ケリー『ナンシー・レーガン―かくされた伝記―』によると、7週間のストライキでレーガンの計算では、俳優は1000万ドルの収入を失い、製作者は5000万ドルの損失を受けたとされた。俳優、製作者共に莫大な金と時間とエネルギーをかけて団体協約を確立している。アメリカでは法に基づくのではなく、契約に基づいて俳優等の利益が守られているのである。法的秩序の形成よりも契約による秩序形成に重点が置かれている。 ECとアメリカを比較すると、「国際的な検討の場においても、米国(著作権法による実演家の権利強化を一切行う意思がない)とEC(許諾権システムを維持したい)の間に鋭い対立が残されている」(「コピライト」No.450 1998年9月号 文化庁国際著作権課「『WPPTプロトコル』に係る日本政府の条文案について」17頁)といえる。「米国は、この条約(筆者注:視覚的実演に係る実演家の権利に関するプロトコル)の検討にあたっても、日本政府が提案することとしていた条約案を事前に阻止するため、日本政府に対して提案を行わないような不当な圧力をかけてきました」(「文化庁月報」平成10年11月 No.362国際著作権課「著作権関係条約の概要とその変遷」10頁)とすれば、アメリカとECの中間的な新たな条文案が提出されることにより、アメリカが妥協を求められることを危惧したものであり、この対立はプロトコル成立のためには大きな溝である(プロトコル不成立を目指すのであれば問題は簡単であるが)。
(3)妥協としてのプロトコル 1998年11月22日付日本経済新聞「春秋」欄はグローバルスタンダード(国際標準)を論じる中で、「市場での勝者がルールを決めるのが米国式なら、みんなでルールを決めてから競走しようとするのが欧州式だ」と述べているが、このことはプロトコル検討の場にも当てはまるようである。この状況の中で、「鋭い対立」を越えてプロトコルを成立させるとすれば、「妥協」が要請されてくる。プロトコル不成立のためには妥協はいらない。しかし、プロトコル成立のためには妥協が必要であろう。 日本案はその観点から提起されたと思われる。常設委員会で日本代表(文化庁国際著作権課 澤西三貴子専門員)は次のように述べている。(WIPO報告書「SCCR/1/9.Prov.1」para.14から)。 「日本代表は、文書SCCR/1/4に含まれている提案を行った。その際柔軟性と選択(flexibility & choice)を重視し、締約国に選択の余地を与える枠組みを提案することにより、可能な妥協点(possible compromise)を探ることを目的としていることが強調された。提案の詳細説明に際し、同代表は、提案の第8条(1)および(2)において、固定された視聴覚的実演に対して、一定の排他的権利が認められているが、第9条(1)が該当する場合には、実演家はこれらの権利を行使できないことを強調した。ベルヌ条約第14条の2の(2)(b)の文言が使用されてはいるものの、その意図は、ローマ条約第19条と同じ意味をもたせることにあった。しかしながら、報酬請求権は、国内立法によって定められることが想定(expect)されていた(第10条)。このような場合に限り、内国民待遇は、相互主義に基づいて適用され(第4条(2))、遡及的保護は、適用されない(第16条(2))。第9条(2)の下で、締約国は、視聴覚的実演家に対する排他的権利を維持する道を選択できるが、それは、自国民に対してのみであり、他の加盟国の国民である実演家の内国民待遇は行わないものとされている。」 日本案は「可能な妥協点」を提起し、国際的ハーモナイゼーションをはかるためのものであり、このことは文化庁国際著作権課の日本政府案についての次の解説でも読み取ることができる。 「我が国の条文案は、米国もECも国内制度の基本的変更を行わずに批准し得る内容となっており、『我が国は、自国の制度を利己的に主張するのではなく、国際的ハーモナイゼーションに貢献することを主眼とし、米国・EC等各国の異なる制度に配慮しつつ、多くの国が批准し得るフレクシブルな条文案を提案した』ということを堂々とアピールできるものとなりました。 したがって、我が国の条文案は、(その内容の詳細が多くの国の支持を得るかどうかは別として)国際貢献を目指す我が国の姿勢について、各国の評価を得る可能性を持つものとなっています。国内における関係者間の検討の遅れが偶然にもこうした幸運な状況をもたらしたことは皮肉ですが、結果としては、国際的ハーモナイゼーションの達成に向けた貢献という日本の姿勢を、強くアピールできることとなったのです。」(「コピライト」No.450 1998年9月号 文化庁国際著作権課「『WPPTプロトコル』に係る日本政府の条文案について」17~18頁) 視聴覚的実演に関する議定書(プロトコル)作成に至るには、上にみるように3つの道があるように思われる。実演家の団体の立場からいえば、権利の基本原則をひたすら強く主張し、後は政府に委ね、主張が通らない場合は政府を批判する方法が姿勢としては楽である。現に組織の歴史はそのような方法で来たことを示している。しかし、もはやそうした時代は終わったのではないか。条約にせよ法律にせよ、法的規範作成の現場は政治的交渉の場であり、しかもそこでの諸状況は常に変化しており複雑である。その中で目的を達成しようとすれば、原則に立脚しながらも妥協を探る他はない。当事者である実演家自身がまずその努力をしなければならない。
● 常設委員会の中心課題の「権利の移転」
視聴覚的実演の保護は11月2、3、4、日に検討された。検討項目は、「条約の表題と性格」「実演家の定義」「視聴覚固定物と視聴覚著作物の定義」「内国民待遇」「人格権」「貸与権」「放送と公衆への伝達に関する権利」「制限および例外」「契約の取極および権利の移転」等である。この中でも重要課題は「内国民待遇」と「契約の取極」および「権利の移転」である。ここでは、実演家の立場から「権利の移転」「契約の取極」をみておきたい。
(1)アメリカ案、日本案における「権利の移転」「契約の取極」 ECとその加盟国の提案では権利の行使に関して権利の移転あるいは契約の取極という考え方はとっていない。これに対してアメリカ案は、実演家がその実演を視聴覚著作物に固定することにいったん同意した場合には、書面による契約に別段の定めがない限り、実演家の排他的権利は製作者に移転する(報酬請求権には適用されない。また締約国に報酬請求権の創設を求めるものでもない)という提案である。 このECとアメリカの間にあって日本案は、視聴覚固定物に固定された実演に関して一定の排他的権利を実演家に与えるが、実演家がその実演の視聴覚固定物の製作に寄与することを約束したときは、反対の又は特別の契約がない限り、利用に反対することができないとしている。また、締約国は自国の国民である実演家にはこれを適用しない国内法を定めることができるとし、さらに、締約国は国内法で実演家の報酬請求権を定めることができると提案している。 常設委員会では日本、アメリカ、EC各代表は次のとおり発言している(WIPO報告書「SCCR/1/9.Prov.1」para.105,106及び114から)。 「日本代表は、同国の提案が、映画の著作物の製作に寄与した実演家および著作者それぞれの権利の間にバランスを取る必要性を考慮していると説明し、ベルヌ条約第14条の2の(2)(b)およびローマ条約第19条を参照すべき規定として採用した。実演家に寄与される権利は、それと相反する反対の、または特別の契約がない限り、行使され得ない。同代表は、同提案の主な目的は柔軟性を持たせることであり、締約国はこのような制度を適用しない国内法を制定または維持できると付け加えた。」 「米国代表は、同国の提案が国際的ハーモナイゼーションおよび適正なレベルの確実性を達成する明確なルールを定めており、実演家の保護を報酬請求権を規定することによって行うか、または団体協約もしくはその他の種類の契約によるのかにつき、各国に柔軟性を持たせていると強調した。同代表は、同提案が定めようとする反論可能な推定譲渡は、法令または契約交渉により確立される報酬請求権ではなく、実演家の排他的権利のみに適用されると述べた。同代表はまた、徴収団体により管理され得る実演家の報酬請求権を各国が規定するのは自由であると述べた。」 「EC代表は、権利の移転の問題は国内法に委ねられるべきであり、視聴覚的実演家の保護に関する国際文書により対応すべきではないという見解を述べた。同代表は、WPPTには本件に関する記載がないと指摘し、条約または議定書ではなく国内レベルで解決を図るよう主張した。」
(2)「権利の移転」「契約の取極」に関する国際実演家団体の意見 WIPOの実演家のNGOとしてFIA(国際俳優連合)、FIM(国際音楽家連盟)等がある。FIA、FIM共に実演家の排他的権利の移転、また、契約の取極のない場合の権利不行使について反対している。 ジョン・モートンFIM会長は次のとおり意見を述べた。「FIMとしては国内法で権利の推定譲渡を規定することには反対であり、これを国際条約で規定することには一層強く反対する。反論が可能である場合にも受け入れられないが、反論できない場合には一層受け入れられない。委員会は次の3点を考慮しなければならない:推定譲渡が現実に必要なのかどうか、それが原理的に望ましいものであるのかどうか、そして均衡をとるためにそれが必要とされるのかの3点である。実演家のNGOは視聴覚固定物の製作者と実際に交渉をした経験を持つ人々を代表し、またそういう人々から構成されるものである。このような固定物としては音楽ビデオ、CDプラス、テレビ番組・映画、記録映画、フィルムまたはテープによるコンサート、オペラまたはミュージカルの記録、マルチメディア製作物、長編映画などがある。あらゆる権利が交渉の対象となる。成文法で定められた実演家の権利は、第三者の対抗を保護するとともに、公正な取引の基礎となるものである。必要なのは自由市場―対等な交渉の場―である。権利の推定譲渡は―たとえ反論が可能であっても―自由市場のメカニズムを干渉するものである。実演家に個別交渉、団体交渉の力が共にない場合には、推定譲渡は実演家の地位を悪化させる他ない。 次に推定譲渡が原理的に望ましいものであるかどうかを検討してみよう。推定譲渡を規定すれば、実演家のための議定書であるはずのものが、製作者のための議定書になってしまう。カナダの提出文書が示すように、そのためには製作者の身分について詳細に論じ、その結果を投票にかける必要が生じる。そうすれば実演家の排他的権利の性格についてすでに行われた討議の大半が無意味になってしまう。デンマーク代表が示唆したように、多数の国に、現在の基準を低下させるか、議定書を拒否するかの二者択一を迫ることになる。人格権に関する討議の間に、提案された規定は最低限度を定めるものであって、国内法でこれより改善することができるという発言があった。しかしこれは権利の推定譲渡については通用しない。推定譲渡の規定はあるか、ないかのどちらかしかあり得ない。―中間的な規定という道はない。本議定書おける推定譲渡の規定は、保護に2つの異なったレベルを持ち込むことになる―WPPTが音声の実演について定めた保護水準と、それより低い、議定書の保護水準である。経済の法則(「グレシャムの法則」〔筆者注:悪貨は良貨を駆逐する法則〕)が働いて、保護は低い方の水準に流れがちになるに違いない。 最後に『推定譲渡』が均衡をとるために必要かどうかという問題である。私としてはベルヌ条約第14条の2との関連性を論じたいと思ったが、多数の代表は、この目的に関しては、同条の適用範囲が限られていて、また不適切であることを明確に説明した。 リケットソン教授は、ベルヌ条約に関する、権威ある著書の中で―多数の識者の見解では―実態的権利の承認と保護を本質的な対象とする条約には、権利の利用に関する条約を律する規定はなじまないと指摘している。『私的契約は国内法が対象とする問題にとどまる』と同教授は述べている。 我々もこの見解に同意する。この第14条の2全体がこの議定書に適用されたとすれば、次のような問題を伴うことになる。
- 推定譲渡の規定は、実演家も映画の著作物の著作権者である国(がもしあるとすれば、そういう国)だけに適用されることになる。また、
- 音楽の著作物の実演家には、国内法で適用法を定めていない限り―この問題については条約はいずれとも定めていない―適用されないことになる。また、
- 特定の映画の著作物の使用による実演の利用にのみ適用されることになる。
(3)芸団協の意見 芸団協はWIPOにおいては次の考えに立って、視聴覚的実演に関する実演家の権利を具体的に主張してきた(1998年6月のWIPO専門家委員会での芸団協発言から)。
- 情報のデジタル化、ネットワーク化の急速な発展は実演の利用に重大な影響を与えており、実演家の経済的、人格的権利について国際的ルールを早急に確立すべきである。
- 実演は著作物同様、知的創造行為の所産であり、実演家の権利は著作権そのものとは概念されないものの、権利の内容は著作者の権利と同等であるべきであり、権利のあり方からいえば、実演のすべての利用について実演家の権利が及ぶべきである。
- そして、固定された実演に関しては、映像に係る実演と音に係る実演を差別することなく、すべての固定された実演も保護の対象となるべきである。
(4)常設委員会におけるFIA、FIM、芸団協の立場 常設委員会において実演家のNGOとして、FIA、FIMは「権利の推定譲渡」「契約の取極」に反論し、アメリカ案、日本案に反対の立場にある。芸団協は「権利の推定譲渡」に反対であるが、日本案は基本的には積極的評価をしている(但し、個別的条項について、定義、人格権、放送及び公衆への伝達に関する排他的権利、貸与に関する排他的権利について意見を国内で提出している)。 常設委員会において、芸団協は個別的条項に関して、意見を述べる予定であったが、日本案を評価する立場を基本的にとりながら、一方で具体的問題を出すと、日本の実演家が日本案に反対であり、日本の国内が統一されていないという誤解を生むといけないので、人格権を主張するにとどめた。逆に、日本案を支持する見解を表明した場合、FIA、FIMとの立場に差が生じ、世界の実演家の考え方が割れている印象を与え、プロトコル検討の継続そのものを危くするのでそれは避けた。このことは1998年6月の専門家委員会のFIAの状況に似ている。6月はFIAの主要メンバーであるアメリカ映画俳優組合(SAG)がアメリカ政府案を支持したため、FIA内部の調整が必要となった。今後、この点につき実演家の組織間の調整が要請される。
● いま必要とされる3つの動き
WIPO著作権・著作隣接権常設委員会の次回会合は1999年5月が予定されている。それまでに、わが国の実演家が取り組みを解決しなければならない課題が大きくは3つある。国際的場における課題、国内における課題、それと実演家の組織内における課題である。 国際的場の問題としては、プロトコルに関してFIA、FIMと共に世界の実演家の合意をどう形成するかである。 国内における課題は、文化庁の「映像分野の著作権等に係る諸問題に関する懇談会」(映像懇談会)で合理的な結論を今年度中にどのように出すかである。この懇談会には外務省、通産省、郵政省も関わっている。また、政治的なサポートとして音楽議員連盟も映像における実演家の権利の明確化には強い関心を示しているところである。 3つめは、芸団協が関係団体の協力を得て現在推進している実演家著作権隣接センターの見直し、拡充を早急に仕上げることである。この3つは互いに関連しており、これらの課題を統合的に解決することで、視聴覚固定物に関する実演家の権利という1990年代における大きな宿題に答えを出すことができる。 なお、1998年10月2日の映像懇談会で芸団協は次の提案を口頭で行っているので参考として追記しておきたい。 「映像の複製、放送、有線放送、頒布、利用可能化、送信、貸与等実演の利用について、実演家には基本的には許諾権が与えられるべきであります。著作隣接権制度においては許諾権が基本であり、許諾権があればこそ実演家は、映像の利用について、製作者に安心して協力し得るのであると考えます。現在も、テレビ番組のビデオ化等の目的外利用については実演家には許諾権がありますが、現行法が施行された昭和46年から芸団協が行ってきたテレビ番組の目的外利用で許諾できなかったケースは殆どありません。 しかし、制度上、許諾権を認めるだけの規定では、実際の映像の利用に安全性を欠くということで強い反対があるのであれば、折衷案として、WIPO議定書に関する日本政府案に示されているように、『実演家がその実演の映像の製作に寄与することを約束したときは、反対又は特別の契約がない限り、映像の利用について反対することができない』という定めを検討することもやむを得ないと思います。ただし、この場合、実演家は衡平な報酬を請求する権利をもつことが規定されることが絶対の条件であります。そして、その実際上の権利行使の方法としては、一つの映像作品に関わる実演家は多数に及ぶことを考えますと、団体による包括的な権利行使システムによることが適切であると思います。 なお、人格権は実演家にとって財産権同様に重要な権利であります。映像に関しては制作、監督、演出、撮影、美術等を担当して全体的形成に創作的に寄与した人が著作者であり、人格権をもっております。著作者との均衡から言って、実演家にも当然に著作権法上人格権が与えられてよいと思います。財産的権利と異なり、人格権は立場の違いが利害損失にかかわるというものではなく、製作者も実演家も同じ立場であると考えます。実演家の人格権が侵害される場合は、製作者、監督等の人格権も又侵害されているからであります。 本年3月に発表された文化庁の「文化振興マスタープラン―文化立国の実現に向けて―」は、『メディア芸術は、21世紀の我が国芸術の中心の一つとして発展していくことが期待されており、今後、メディア芸術の振興を図るための諸施策を「メディア芸術21」と位置づけ、その一層の推進を図っていく』と述べていますが、そのためには情報化の進展や国際的動向に対応した著作権制度の見直しは重要であると考えます。 映像産業、映像文化発展のためにこそ、製作者、著作者、実演家が一体となって『良いルール』をつくることが必要であることを強く主張いたします。」
(資料翻訳は松居弘道氏の協力を得た。)
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。