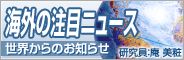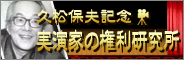著作権情報センター発行「コピライト」500号特集(2002.12)から同誌の了承を得て転載(2008.12) 前編
棚野正士備忘録
【芸団協とともに30年〜忘れられない人々〜】
社団法人日本芸能実演家団体協議会前専務理事 棚野正士(現IT企業法務研究所) 聞き手 コピライト編集長 射場俊郎
芸団協との出会い
―棚野さんは、この6月(2002年)に退任されるまで、ちょうど30年間、芸団協とともに歩んでこられました。まず芸団協に入られたいきさつから。 「私が芸団協に入ったのは昭和47年8月でした。46年まで東京フィルハーモニー交響楽団の事務局にいまして、その後、オペラ図書の出版社を作ろうと準備していたんですが、日本演奏連盟事務局長の西宮安一郎さんから、芸団協の広報委員会を手伝えと“命令”されまして(笑)。46年に施行された新著作権法の、実演家の権利についての啓蒙パンフレットや、機関誌をつくるのを手伝ったのが、芸団協との出会いです。 広報委員会には西宮さんの他、現在も第一線で活躍している俳優の江見俊太郎さん(故人)、亡くなった能楽の桜間金太郎さん、落語の柳家つばめさんたちがいました。 西宮さんは舞台入場税撤廃運動を永い間リードし、青木正久衆議院議員と一緒に音楽議員連盟を作り上げた、実演家の運動にとっては忘れられない人です。私は東フィル時代から西宮さんの後にくっついて運動していたんで、命令には逆らえません。(笑)」
―広報委員会を手伝っていたことから、芸団協に入ろうと思ったのは? 「私が芸団協という団体に関心を持ったのは、著作権法95条の「商業用レコードの二次使用」に引き付けられたからなんです。私は学生時代から、近代市民法としての一般私法が発展して社会法が生まれる、という考えに法のロマンを感じていたんですが、この条文の立法趣旨が、機械的失業に対する全体的な補償であると聞いて、長い間探していた恋人にあったような気がしました(笑)。当時の私は、95条が著作権法全体の将来の姿を先取りしていると思ったんですね。」
―商業用レコードの二次使用の規定が、著作権法の将来の先取りというのはどういうことですか? 「その頃の私は、商業用レコードの二次使用料は、機械的失業への補償という立法趣旨に沿って、個人分配より実演家全体のために使われるものだと思ったんです。文化庁からも、そのような考え方を聞きましたしね。将来の著作権法はこのような社会法的な考え方を取り組り込んでいくのではないか、というわけです。 結果的には、それは私の片思い(笑)だったというか、後になって、こうしたいわば団体主義的な方法は、発展途上の過渡的なものだと思うようになりました。それでも、95条は個人の権利と全体の利益の調和を考える上で、私はいまでも強く魅かれています。」
―入られたころの芸団協はどんな様子でしたか? 「事務局次長ということでしたが、次長といったって、渡辺廣次事務局長と私、それに女性が2名いただけです。事務局は新橋の藤田ビルで、古い小さな建物の中に著作権資料協会、今の著作権情報センターも一緒でした。 会長は2代目の坂東三津五郎さん、副会長は紙恭輔さん、初代専務理事の久松保夫さん、加盟団体は42団体でした。」
久松保夫初代専務理事
―今日は、棚野さんの芸団協生活の中で、もう亡くなられたけれども忘れられない人たちについて話して頂きたいと思います。まず芸団協の生みの親の一人、久保保夫さんについて。身近に接してどんな人でしたか? 「とてつもなくスケールの大きな人でしたね。有名な俳優で優れた組織人で、芸能・民俗学、古文書などの分野の研究家で、有数のこけしの収集家で‥。その一つ一つが高い山のようで、それらが連なって山脈になっているという感じです。久松さんがいつも言っていたのは、実演は創造的活動であるということでです。『忘れられている著作物』という著書の中でも『演技者の側から見れば、台本も楽譜も自分の足がかり、素材にすぎません。』『演技者は作者の創り出した世界の枠を乗り越えて、次元の異なるところで独自な精神的・肉体的創造活動をするのがその使命なのです。』と書いています。これが、久松さんが芸団協の活動にあれ程情熱を注いだ原点だと思いますね。
芸団協が燃えた主催公演
―芸団協の主催公演も久松さんが提唱したそうですね。 「ええ、久松さんは、芸団協の活動は、実演家の権利を守るとともに、芸能活動の推進がもう一つの柱でなければいけない、という考えでした。その信念と、芸能の研究家としての見識を生かしたのが、昭和50年2月に国立劇場で行なった、第1回の主催公演『道成寺のさまざま』でした。 これは、能の『道成寺』、文楽の『日高川入相花王』、壬生狂言の『道成寺』、山形の黒川能『鐘巻』、沖縄の組踊り『執心鐘入』、薩摩琵琶の『道成寺』を一堂に集めたものです。まさに、あらゆるジャンルの実演家が集まった芸団協ならではの企画ですよ。芸団協としても、公益法人としての芸団協の姿勢を初めて世に問うんだということで、組織全体が燃えましたね。 久松さんは早くから黒川能や沖縄の組踊りに関心をもって研究していた人で、その蓄積と、公演のプロデューサーを受け持った、ふじたあさやさんの力量が一つになって、大きな花を咲かせたんです。公演の後でふじたさんも、『国際をもじった“学際”という言葉があるが、これはまさに“芸際”だ。芸団協の本質に根ざしている。』と言っていました。 実は、公演の直前に坂東会長が急逝されて、芸団協は大きなショックを受けたんですが、後任の会長を要請された中村歌右衛門さんが、この主催公演をご覧になって決意された、と久松さんから聞きました。実際に歌右衛門さんは後々までこの『道成寺のさまざま』の思い出を、楽しそうに話しておられました。」
ヒューマニズムと聖書
―久松さんは在任中に亡くなられたんですね。 「昭和57年6月15日、日本民間放送連盟との会議に、入院中の病院から出席したんですが、会議中に呼吸困難を訴えて救急車で運ばれる途中、急逝されました。芸団協のために殉職されたといってもいい。 久松さんは、亡くなる一年前くらいから体調を崩して入院生活を送っていましたが、枕元には、青山学院大学神学部の頃からの聖書がいつもありました。その聖書はどのページにも、余白に小さな字でびっしりと書き込みがあるんです。余白が無くなると付箋を貼り、付箋が何枚も重ねられているページもあります。 久松さんは奥さんに、自分にもしものことがあったら、この聖書を柩に入れてほしい、と話していたということで、奥さんはそうするつもりでした。この話を聞いた黒柳徹子さんが電話をしてきて、ちょうど久松さんの家にいた私がその電話を受けたんですが、黒柳さんが、『聖書は棺に入れないで残して下さい』と言うんですね。奥さんは『主人の言い付けに背くけれど、私が後から持って行きましょう。』と言われました。いまも、久松さんの聖書は奥さんの許にあるはずです。 久松さんがよく私に、「ぼくの心の奥にあるのはヒューマニズムと庶民の心だ。」と言っていました。そのヒューマニズムを支えた根底に聖書があったのでしょうし、庶民の心の先には、こけしや民俗学があったのではないでしょうか。 久松さんは、著作権法の条文の冊子にも、聖書と同じように余白にびっしり書込みをしていました。」
―久松さんは、多くの文献も残しています。 「『忘れられている著作権〜芸能人は法律でどのように護られているか〜』という名著がありますし、著作を集めた久松保夫著作集『役者人生奮戦記』などがあります。この著作集は、久松さんと一緒に芸団協を作り上げた、俳優の大宮悌二さんが編集したものです。久松さんの後を承けて専務理事として組織の発展に尽くした、俳優の小泉博さんは、『この著作集は、これから芸団協事業を受け継ぐ者達や新しく参画してくる者たちにとって、多くの示唆を含む貴重な文献となることは間違いありません。』と書いています。 大宮さんは、芸団協で実演家の福祉と労災の問題に全力で取り組んだ実演家です。この人がいなければ、芸能人年金制度はできなかったと思いますね。」
二人の事務局長
―事務局にはどんな方がいましたか? 「私が芸団協に入った時は、渡辺廣次事務局長でした。渡辺さんは、専任者としては事実上初代の事務局長で、芸団協事務局の実務体制を一から作った人です。 陸軍士官学校を出た職業軍人で飛行機乗り、戦後は東大の哲学科に編入学、その後会社の経営もした、という経歴の持ち主でして、病院で療養中に知り合った大宮さんが久松さんに紹介して、昭和46年に芸団協に入りました。元軍人らしく『事務局長は参謀だ。』が口癖で、私は毎晩のように新橋で飲めない酒を御供しながら、参謀の職責とは何かを聞かされました。私は軍隊を知らないので、参謀といわれても本当のところはわかりません。要するに番頭のようなものだろうと。勝手に解釈していました(笑)。 渡辺さんは、事務局長在任中の昭和51年に急逝されましたが、5年間の在任中に果たした役割は本当に大きいと思います。芸団協は久松保夫なくしてはありえなかったと思いますが、実はその傍には、渡辺廣次という名参謀が居たんです。 渡辺さんは『史石』という号を持つ書の大家で、見事な字を書きました。渡辺さんには字の手ほどきも受けたいと思っていましたが、『君の字は、字とは言えない。』と断れたりして‥(笑)。酒も字も不肖の弟子でした。」
―渡辺さんのその後は? 「和沢正次(昌治)さんです。和沢さんは、入場税撤廃運動や福祉問題への取り組みなど、2年間の任期でその何倍もの仕事をされました。 役者であり、運動家であり、すぐれた文学者でもあった多才な方です。『犀川べりで』という作品で泉鏡花記念金沢市民文学賞を受けています。 私はこの二人の事務局長から教えを受けました。二人とも亡くなられましたが、30年たった今も、二人の教えを越えられないような気がします。」
中村歌右衛門前会長のこと
―中村歌右衛門前会長とは、22年間まるまるご一緒でした。 「私は今でも、歌右衛門さんのことを思い出すと涙が出そうになります。平成13年3月31日に84歳で亡くなられました。ご遺族の挨拶状に『桜の花と春の雪に見送られて父は逝きました。』という言葉がありましたが、あの日は、満開の桜が散り、季節に珍しい雪が降りました。亡くなる数時間前にお目にかかりましたが、本当に美しいお顔でした。」
―芸団協会長としての歌右衛門さんは? 「歌右衛門さんの人と芸について、早稲田大学名誉教授の河竹登志夫さんは、『山ならば富士山にもたとえようか、当代歌舞伎界において、孤高とも言えるほどに抜きん出て頂点に立つ人。』と書かれています。また、文化庁長官だった佐野文一郎さんは、『芸団協は歌右衛門会長の下で、権利者の強固な団体であると同時に、芸術家の団体としての確かな品格をも備えようとしているかのように見える。』と書かれています。 芸団協は、あらゆるジャンルの実演家が6万5000人集まった、複雑で多様な組織ですが、トップに歌右衛門会長を頂いているということで求心力が働くというか、全実演家を結集しようとする芸団協の中心柱としての存在感は本当に大きかったですね。」
―歌右衛門さんが力を入れていたのはどんなことですか? 「芸団協の頂点に立つ者として、いつも頭から離れなかったのは、“芸術家の社会的地位”ということだったと思いますね。芸団協の機関誌にも『芸術家の問題は煎じ詰めると“敬意の獲得”でしょう。』ということを書いています。別のところでも、『外国で痛感するのは、芸術家の地位の高さです。文化行政においても重要なポストを任せられたり相談を受けていますからね。何といっても芸術のことは芸術家がいちばんよく知っているに決まっているのだから。』と話しています。 芸団協内部で、レコードの二次使用料分配をめぐって意見が分かれたときは、私に『芸団協は芸術家の団体か、世の中の渡り方をやるところか、どっちなの?』と厳しい口調で言われたこともありました。」
歌右衛門さんと著作権
―著作権の問題について、歌右衛門さんはどのように考えていらっしゃったんですか? 「歌右衛門さんは多分、著作権法の細かな条文はご存知なかったと思います。しかし、たいへん勘がいいというか、洞察力の鋭い人で、私は著作権問題の考え方について、随分教えられました。 歌右衛門さんが事あるごとに強調していたのは、実演はその場にいて生で見、聴くことが命だということです。そのことは、『お芝居は劇場の空間を伝わってくる味わいが大切です。』とか、『刻々とあらわれては消えていく、そこにこそ生命ある美の輝かしさがあるのです。』という言葉によく表れています。 それだけに、舞台中継や録画には慎重でした。中継する放送局に注文を付けることもあったようです。舞台中継を市販ビデオにすることにはとても保守的で、内容を点検してなかなか首を縦に振ってくださらない。最終的には了承してくださるんですが、ビデオ製作会社との間に立つ芸団協事務局としては大変でした。 歌右衛門さんから急に、歌舞伎座に来てほしいと呼ばれたことがありました。『ある民間テレビ局が、深夜に“録画チャンネル”という番組を始める計画で、第1回に歌舞伎座の中継が予定されている。録画を勧めるような番組は、著作権的におかしいのではないか。』ということでした。結局、歌舞伎座の役者たちは中継を断りました。 実演家の権利を拡大すると、コンテンツの利用が難しくなる、という声に対して歌右衛門さんは、『実演家の権利が認められていないから作品を出さないのです。権利が認められれば安心して出せます。』と言っていました。このことは藤原浩弁護士が述べています(『コビライト』本年(2002年)10月号講演録)が、問題点をズバリとついた言葉です。」
―私的録音録画問題については? 「この問題は昭和51年、芸団協が最初に、“西ドイツ方式”の導入を文化庁に要請したんです。歌右衛門さんも強い関心を持っていました。検討がなかなか前へ進まなかった頃、江戸っ子の歌右衛門さんから『まだなの。早くなさいよ。』とよく叱られましたし、ご自分で海部総理を訪ねて、芸術文化振興基金のお礼を兼ねて直接要請したこともありました。 ただ、歌右衛門さんの関心は、補償金への期待というより、機器の発達で家庭内の録音録画が氾濫することへの心配のほうが強かったと思います。昭和58年に、補償金制度の実現を目指してJASRAC、日本レコード協会と一緒に日本音楽著作権・著作隣接権団体協議会を作った時の記者会見で、録音録画機器の発達についてどう考えるか聞かれて、『そうですねぇ。便利なような、そうでないような。でも、やっぱり、お芝居は劇場で見てほしい。』と答えています。」
―身近に接した歌右衛門さんは? 「歌舞伎界の最高峰、文化勲章受章者、人間国宝という堅苦しさのない、気さくでやさしい人でした。脇役の俳優さん、まだ若い俳優さん、裏方の舞台技術の人たちを大切にされました。優れた脇役がいて主役が生きる、ということを、『魚は頭と尻尾だけでは食えないよ。』という言い方で教えていただきました。 昭和60年に佐渡で、『第1回全日本子どものための舞台芸術大祭典』を開催した際、名誉会長を務めた歌右衛門さんは、記念公演で、『隅田川』を演じたんですが、その時同じ舞台で地元の子供たちの歌舞伎『絵本太功記』を演ずることになっていたんです。地元では、歌右衛門さんの踏む舞台に子どもを立たせていいものだろうか、と心配して私に相談があったんですよ。歌右衛門さんに聞いたら、即座に『いいじゃないの。子ども衆(こどもし)に負けないように、私やるよ。』 佐渡の子ども歌舞伎は、長い歴史がある伝統芸能なんですね。歌右衛門さんは、子ども歌舞伎を事前にビデオで見ていたんです。打ち合わせに伺ったとき、『本当によいものを見た。子ども衆の純な心が伝わって、口では言えないいいものだ。』と、涙ぐみながら話しておられました。 『隅田川』は熱のこもった見事な舞台でした。歌右衛門さんと佐渡の子どもたちのお付き合いはその後も続いていて、病床の歌右衛門さんに、佐渡片野尾小学校の子どもたちからお見舞いの便りが届いたそうです。 国立劇場の舞台に本物のお猿さんを上がらせたのも、歌右衛門さんですよ。芸団協の主催公演『道ゆく芸能』の時で、周防の猿回しが演目にあったんです。国立劇場の側は、人間国宝も演じる舞台を猿に踏ませるなどもってのほか、というわけです。どうしても必要だからと粘ったら、『歌右衛門さんがよいとおっしゃるなら。』と折れてきた。歌右衛門さんに話したら、一言『お猿さん?あら可愛いじゃない?』(笑)一件落着でした。」
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。