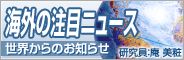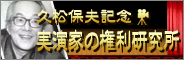著作権情報センター発行「コピライト」500号特集(2002.12)から同誌の了承を得て転載(2008.12) 後編
棚野正士備忘録
【芸団協とともに30年〜忘れられない人々〜】
社団法人日本芸能実演家団体協議会前専務理事 棚野正士(現IT企業法務研究所) 聞き手 コピライト編集長 射場俊郎
黒川徳太郎さんのこと
―芸団協の活動を外から支援した人たちも多かったと思います。中でも忘れられない人は? 「数え切れない程多くの人たちに力を貸していただきましたが、亡くなられた方の中では、NHKの著作権部長だった黒川徳太郎さんですね。 実演家は、新著作権法で著作隣接権を認められ、特に放送事業者との間で新しい関係を結ぶことになりました。芸団協はNHK、民放連と、放送番組の保存や使用、商業用レコードの二次使用料、リピート放送料などについて、基本的な契約を締結していましたが、芸団協側の久松専務理事の折衝相手がNHKは黒川さんでした。随分厳しい折衝だったようですが、その時に黒川さんと久松さんの間でできた信頼関係と秩序が、その後の芸団協と放送事業者の間の信頼関係の基になったと、私は今でも思っています。」
―黒川さんは、著作権や著作隣接権に関する文献を数多く翻訳しています。 「芸団協では、ベルギーのルウバン大学のフランク・ゴッチェン教授の著書『ヨーロッパ経済共同体における実演家の権利』と『実演家の契約』を黒川さんに翻訳していただいて、発行しました。この2冊は芸団協の運動の理論的な柱になったし、私にとってバイブルのようなものです。 ゴッチェン教授はこの著書の中で、『著作隣接権による実演家の保護が、著作権の保護のレベルより下回るべきだという論には何ら根拠はない。二つの権利に上下関係はなく、二つの自律的な権利の組合せがあるというべきだ。』と言っています。芸団協は昭和58年に、実演家の権利を抜本的に見直す必要があるという要望書を、文化庁長官に出したんですが、ゴッチェン教授の著書から沢山の示唆を受けました。 芸団協が翻訳をお願いしたものだけでなく、黒川さんが著作権資料協会の仕事で翻訳された沢山の文献は、私たち実演家や運動を進める者にとって、実践に役立つ大変貴重なものです。まだまだ教えを受けたい方なのに、平成9年に急逝されました。本当に残念です。
商業用レコードの二次使用料分配
「黒川さんに教えられたことの一つに、商業用レコードの二次使用料の問題がありました。前にお話したように、私はこの制度は個人の権利というより実演家全体のためのものだと考えていました。立法者の文化庁もそうした考え方だったのです。ですから、芸団協は制度が出来てから長い間、二次使用料を個人には分配しないで、団体分配していました。 しかし、黒川さんはこうした考え方には批判的でした。よく私に、二次使用料は個人に分配すべきだと言っていました。個人に分配しないのは、立法趣旨からではなく、まだ放送事業者から受け取る金額が少ない上に、分配のためのデータが無いからではないか、というわけです。 その後の芸団協の動きは、黒川さんのいう方向に進みました。昭和52年に大阪芸能労働組合(大芸労)が芸団協を相手に、『商業用レコードの二次使用料は、立法の趣旨から見て機械的失業に対する実演家全体への補償だ。』という理由で、二次使用料の分配を要求する訴訟を起こしていたんです。しかし裁判所は大芸労の主張を退けて、『二次使用料を受ける権利が、商業用レコードに収録された実演と無関係にすべての実演家に帰属すべきものと解する余地はない。』という判決を下しました。 こうしたことなどから、芸団協では昭和61年から団体分配の基本的見直しを始めました。これが、平成5年の実演家著作隣接権センター(CPRA)の発足につながった訳です。平成11年度からは、団体分配を止めて基本的には個人分配の方向になりました。」
河野愛さんのこと
―大芸労の主張は、文化庁やかつての芸団協の考えと同じに思えますが? 「この訴訟のために芸団協と文化庁で、二次使用料の定めについて根本的に検討した結果、『分配は指定団体の内部法理に属する』という基本的な考え方を確認しました。この時適切な助言を示してくださったのが、当時文化庁著作権課の法規係長だった河野愛さんです。 河野さんは、行政官としても、横浜国立大学助教授の研究者としても、本当に優秀な人でしたね。芸団協の設立25年の時の機関誌で、筑波大学の斉藤博教授(現在、専修大学)と横浜国大の河野さんにお願いして、実演家の権利を考える座談会をしました。その中で河野さんは『実演は実演家が自分の精神活動によって生み出さなければ生まれません。そういう意味では著作物の創作に際しての精神活動と実質的に差がない。』と言っています。 河野愛さんは、その名のとおりみんなから愛された人でした。文化庁の伝統文化課長の時、遠山敦子長官と二人で秩父の夜祭りに行って徹夜し、朝帰りで役所に出勤したと、茶目っ気たっぷりに話していたことを思い出します。平成8年の2月に訃報を聞いたときは、大きな牡丹の花が突然地に落ちたような気がしました。」
クロード・マズイエさん
―外国の人で忘れられない方は? 「WIPOの広報著作権局長だったクロード・マズイエさんはその一人ですね。WIPOが発行したマズイエさんの『隣接権条約・レコード条約解説』は、大山幸房さんの訳で繰り返し読みました。マズイエさんは大山さんから紹介して頂きました。 マズイエさんには、芸団協が取り組んでいたローマ条約加入に向けた運動のために、何度か来てもらいました。昭和58年に、芸団協の『ローマ条約早期加入を求めて』という集会に招いた時は、講演で『実演家は文化と芸能の分野でその国を代表する大使だ。その特別な立場は保護されなければならない。』と話されていました。 講演の翌日、マズイエさんは、文化庁の佐野文一郎長官を訪ねました。私も同席しましたが、マズイエさんは『長官に初めてお会いしたのはローマ条約が出来て2年目でした。それからもお互いに著作権のための闘士であり続けたが、20年経った今、私はWIPOを代表して、日本のローマ条約加入を要請するためにここに来ました。』と熱心に話されていたことを覚えています。二人の著作権の闘士の話し合いは、実に印象的でしたね。 冗談の好きな人でした。最初の芸団協訪問の時は、新橋の小さなビルにいた頃で、日本人でも二人乗るのがやっとというエレベーターに、窮屈そうに巨体を押し込んで、『今度来る時は、芸団協がもう少し大きなビルに居るように期待するよ。』と言っていました。」
―ああ、あの「棺桶エレベーター」(笑) 「秋葉原に行った時は、息子さんのためにソニーの製品を買って、『Sony for son』(笑)。その息子さんのパトリック・マズイエさんは、今お父さんの後を継いでWIPOで活躍しています。」
芸団協の新しい展開
―設立から35年余り経った芸団協は、昨年(2001年)の定款変更で大きく変わったように思われます。 「定款変更の主な点は3つありました。 1つは、芸団協の目的に、著作隣接権者の権利の擁護を明記したことです。昭和40年の設立の時は、新著作権法ができる前でしたので、このことがはっきり書かれていません。 2つ目は、正会員の資格を拡大したことです。設立以来、芸団協の正会員は『専門芸能実演家の団体』に限っていましたが、新しく『実演家の著作隣接権を管理し、又は擁護することを主たる業務とする者の団体』、これは日本音楽事業者協会や音楽制作者連盟のような実演家を抱えた事業者の団体のことです。それと、『実演を援助し、充実させることを主たる業務とする者の団体』、これは照明家や舞台美術家のような舞台を支える人たちの団体のことです。その2つを正会員に加えました。正会員の拡大は、野村萬会長の基本理念に沿うものだと、私は思っています。 3つ目は、実演家著作隣接権センター(CPRA)の位置付けです。これまで芸団協は、実演家の著作隣接権の管理を主軸に、芸能に関する調査研究や、公演、実演家の福祉まで幅広い事業を、理事会と、諮問機関としての委員会で行ってきたんですが、事業が拡大し、専門化するにつれて、理事会がすべてをコントロールすることが難しくなってきた。とくに権利者の財産権を扱う業務は、高度な専門性が必要で責任も重い。そこで、芸団協の業務の中で、実演家の財産権を扱う事業を分けてCPRAの業務として、CPRAの運営委員会がその業務を行うことにしました。」
野村萬会長〜狂言師600年のDNA
―芸団協の新しい組織が、野村会長の理念に沿ったものだ、というのはどういう意味ですか? 「野村会長の芸団協に関する理念がよくうかがえるのは、昨年(2001年)、芸団協の機関誌『パフォーマー』に寄せた年頭所感です。この中で野村会長は、世阿弥が『習道書』で、座員各自の協調と調和なくしては一座の成功も繁栄も望めない、互いに譲りあい助けあう心を持って演ずることこそが肝要だ、と説いていることを引いた上で、『演者のみのこととも、一座・一団体のこととも限りますまい。実演家・演出家・制作者など直接芸能の発信に関わる人々、そして、事業者など受信者(観客・聴衆等)との仲立を担う人々、芸能に携わる人々すべてが、個々の利害を超え、【けん・もん・しん】の芸能の原点に立ち帰って、志高く歩みを共にし、力を結集して事に当たることこそ、時代の要請に応え、日本の芸能の未来を切り開く道であろうかと思うのです。』と書いています。 実演家だけでなく、実演に関わるすべての人たちを結集するのが芸団協だ、という考えですね。」
―「けん・しん・もん」というのは? 「野村会長はこう書いています。『「花鏡」において世阿弥はまた、「能の出て来る当座に、見・聞・心の三つあり」という言葉を残しています。能の批評の基準として、視覚美による成果、聴覚に訴える成果、感覚美を超えた内面性による成果の三つの観点を挙げ論じたものですが、現代に敷衍してなお、芸能のすべてを包含し、その神髄を的確に言い得たものとして、広く芸能に関わる者の傾聴すべき論であるように思われます。「見」を主とする芸能、「聞」を主とする芸能、その主眼とするところは異なろうとも、所詮「心」なくしては成り立つべくもなく、はたまた、その比重はともかくも、三者具備してこそ真の芸能というべきではなかろうかと思うのです。』。 野村萬会長は、狂言師として600年のDNAが、体の中に編み込まれている方で、古典演劇600年の遺伝子が芸団協100年の思想をつくる、というふうに私は思います。」
棚野さんの実演家論
―棚野さんは、著作権制度の中で実演家をどう位置付けるべきだと思いますか? 「実演には、著作物の創作に匹敵する創作的な精神活動があると思います。他の著作隣接権者とはやはり違います。しかし、実演家を著作者と同じと考えることには無理があると思います。 著作権制度は、自然人を主体とする『著作者の権利』と『実演家の権利』、それに企業者を主体とする『著作隣接権』の3本柱にしてはどうでしょうか。著作隣接権者には、野村会長の言う、実演家と観客・聴衆の仲立ちをする事業者なども入り、時代とともにその範囲が広がっていくのではないでしょうか。」
35年目に実現した実演家の人格権
―芸団協の長年の願いだった『実演家人格権』が創設され、10月に改正法が施行されました。 「今度の改正は、条約に先立って、音の実演だけでなく映像の実演も含めた人格権であること、これまで実演家の運動が政府に対して陳情するものだったのに対して、自分たちで14の団体と協議を重ねて意見を調整し、解決法を探した結果であるということで、大きな意味があったと思います。
―それにしても長かったですね。 「実演家が人格権の保護を求める声を初めて挙げたのは昭和43年。35年も前のことです。当時運動した実演家の多くはもう居ません。一つの運動が一つの世代で完成するとは限りません。去って行った人たちの意思も引き継いで、仕上げていくんだと思いますね。 私の芸団協での30年は、先達の実演家が残した宿題を少しでも仕上げることだったと思います。言ってみれば、先達の掌の上で動いてきたようなものです。もちろん、時代の変化に応じて、宿題の仕上げ方は変わります。しかし、実演と実演家を信じて、その掌の上で働くことが出来たのは、何より幸せでした。 いつでしたか、新聞にフィレンツェの街づくりの話が紹介されていましたが、その中で長い歴史を持つ街では、「死者を含めた民主主義」で、皆で考えている、という言葉がありました。組織づくりも同じではないかと思いますね。 組織の運動は植林のようなもので、苗木を植えて、あるいは種を蒔いて10年、20年かかって木が大きく育つのに似ています。10年、20年先の文化の森を緑豊かにするために、まずは種を蒔いたり、苗木を植えることが必要ですが、その木を育てる肥料は何かというと、私は基礎研究だと思います。基礎研究は運動に先行します。日本の知的財産権の土壌づくりのためには、今、基礎研究が何より重視されてよいのではないでしょうか。 その意味で、著作権情報センターの付属著作権研究所(阿部浩二所長)の成果に期待しています。『コピライト』をはじめ、情報センターが発行しているいろいろな文献の役割も大きいと思いますね。」
―どうもありがとうございました。
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。